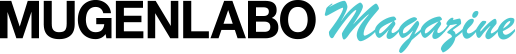- インタビュー
2024年05月31日
超大企業が次々採用「SmartESG」の秘密、独自AIの勝ち筋を聞いてきた【KDDI 推しスタ】

- シェルパ・アンド・カンパニー株式会社
杉本淳 - 代表取締役CEO
さまざまな分野・領域でデジタル化が進む中、時価総額にして数千億円以上の「超」優良企業が続々と導入を決めているクラウドサービスがあります。
「SmartESG」。その名の通り、ESGに関する開示業務を効率化するSaaSです。では一体何を効率化するのか?本稿ではサービスを提供するシェルパ・アンド・カンパニー代表取締役CEOの杉本淳さんにお話を伺いながら、一般の目に触れる機会が少ない「ESG」に関する企業の取り組みについて共有してみたいと思います。
企業がESGに取り組む理由
現在、上場している大手企業を中心に重要性が高まっているのが「非財務情報の開示」です。中心となるのがESG(環境・社会・ガバナンス)に関するもので、ざっくり言うと「社会からの要請に企業がどのように応じてくれるのか」という指標のことです。
例えばどれだけ利益を出していたとしても、近隣の社会に対して公害を巻き散らかす企業は支持されず、結果として持続した成長を期待できなくなります。こうした背景もあり、海外の機関投資家を中心に、企業のESG評価が投資判断の重要な基準となりつつあるのです。
特に時価総額の高い企業ほどESG対応の優先度が上がっていると言えます。
杉本さんはもともと起業前に投資銀行にてアドバイザリー業務にかかわった関係で、ESG評価が企業の格付けや投資家の選別基準となることを経験し、また、その中で企業が直面する課題についても気づいたそうです。杉本さんは状況について次のように説明してくれました。
このESGスコアを海外の機関投資家であったり運用機関はかなり重視していて、基準に達してなかったら投資対象から外したりするわけです。特に海外の機関投資家比率が高いような時価総額で数千億円以上の企業はこの点に対してとても真剣に取り組まれています。
杉本氏
こうした企業の取り組みは各社サイトやレポートとして情報開示しており、例えばSmartESGの利用ユーザーでもある大日本印刷(DNP)では、サステナビリティというタイトルで情報をまとめて発信しています。
では、SmartESGはどのようにして多くの企業の支持を取り付けたのでしょうか?ここには数値では図りづらい「非財務」情報の特徴が鍵を握ることになります。
SmartESGの導入効果

SmartESG(ウェブサイトより)
一般的な株式公開企業が実施する財務情報の開示(決算開示)と異なり、定性的な内容も多く、そのとりまとめや評価の基準も幅があるのが特徴です。杉本さんによるとテーマも毎年変化しており、一度回答したからといってその翌年も同じ回答で全部OK、というわけにはいかないそうです。
企業が自社の取り組みに対して適切な評価を受けるためには、世界に600ほどあると言われるESG評価機関から送られる膨大なアンケートなどに回答しないといけないのですが、これはとても煩雑になっているんです。
一社あたり年間100~300件ものアンケートに対応しているのですが、かなり質問の幅が広くて、例えば環境に関係の深い評価機関から質問があれば、環境の部署に聞く必要がありますし、人の情報であれば人事に聞かないとわからないわけです。
このように全社的に巻き込みながら回答しないといけない。これが最も大変な部分で、一般的な財務に関する開示と大きく異なるところなんです。
杉本氏
また評価機関によって「ESG」に対する注目度も変化します。ある機関は環境を重視し、ある機関はガバナンスに対する視点を強く持つ、といった具合です。この特性に合わせて自社の非財務情報をどのように開示するのか、作戦を練る必要があるのです。さらにこれに加えてデータの問題もあります。
データの特性にも課題があって、財務情報と違って非構造化データ、例えば人権であれば方針を出したりするのですが特に所定のフォーマットなどはありません。みなさんホームページであったり報告書であったり様々な形で開示するので、自社と競合他社などの比較が困難ですし、作戦の練りようがないんです。
杉本氏
この複雑かつ定性的な内容のとりまとめを実現したのがSmartESG、というわけです。アンケートなどで要求される社内の非財務情報の収集から開示、評価対応までの一連の業務をシステム上で一元管理することで、作業効率の大幅な改善を実現します。導入企業のひとつ、大日本印刷への導入事例ではSmartESG導入前の前年と比較して回答作成に要する時間を20%削減できたそうです。そして彼らのもうひとつの特徴、それが独自AIの活用になります。
独自AIによる勝ち筋

国内の伝統的な超大手企業の導入事例が並ぶ
このESGレポートの肝は「どのようにして評価を上げるか」です。つまり、評価機関から英語ベースで出されるアンケートで聞かれている要点を「的確に」理解し、回答することが重要なわけです。SmartESGでは、この「何を聞かれるか」に対して「どう答えるべきか」というマッチングを独自のAIによって実現しています。
AIの活用はよく聞かれます。非財務情報は掲載にルールがないので、情報を拾う範囲が結構大きくなるんです。有価証券報告書であったり、企業のサイトだったり、そういったところをクロールして自動的にデータベースに蓄積をしていくというところがまず一番大きな特徴になっています。
そこから情報抽出や分析をするのですが、「複数のESG評価機関が聞いている類似質問」や「各ESG評価機関が重点的に評価する基準」というものが私たちの中にあるので、要はそこに合致するものを抽出して分析できるようになっています。
杉本氏
SmartESGでは、企業の価値評価に大きく影響を持つ評価機関が評価しているポイントを網羅的にカバーできる情報を持っているそうです。これを企業の非財務情報にヒットさせて、適切な箇所を挙げていく。ここに独自のAI技術を盛り込んだことで効率化に成功し、大手から評価されているポイントになっているということでした。
また、このマッチング技術が優れているからこそ、今後は例えばCO2排出量などのデータ可視化に注力する他社などとも連携し、情報開示から評価分析までトータルでできるプラットフォームのような立ち位置を目指したいというお話もありました。
同社のプレス発表を眺めると、5月に入ってからも相鉄グループや日本触媒、商船三井など国内の伝統的な大手企業の導入事例が次々と並んでいます。従来、コンサルティングファームや専業などが手掛けていた領域ですが、そこのデジタル化に成功しつつあるということで目立った競合もおらず、しばらくこの快進撃は続くのではないでしょうか。
関連リンク
関連記事
インタビューの記事
-

ワークフローが美しい国だから必ず勝てる——フライウィール横山直人氏が語る、AI 時代の日本企業の勝ち筋
2026年02月17日
-

スタートアップに会いたい!Vol.104- 大和ハウス工業
2026年02月12日