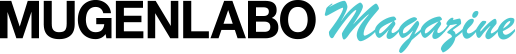- インタビュー
2025年12月02日
1万人組織に生成AIをインストールする方法(前編)——KDDI、全社変革「3つの仕掛け」

- KDDI株式会社
木村 塁 - 経営戦略本部 Data&AI センター長
2023年4月、ChatGPT が世界を席巻してわずか2カ月後のこと。KDDI では生成 AI 活用を全社展開する「KDDI Gen.AI CoE(KGA)」という横断組織が動き始めていた。
旗振り役を担ったのが、経営戦略本部 Data&AI センター長の木村塁氏だ。
当時、多くの企業が生成 AI の可能性に注目しながらも様子見の姿勢を取る中、KDDI は異例のスピードで全社実装へと舵を切る。それから2年。カスタマーサポートでは年間2.4万時間の工数削減を実現し、1万人規模の組織が生成 AI を業務で活用することのできる素地を作り上げた。
大組織がこれほど短期間で変革を実現できた背景には何があったのか。木村氏に2年間の軌跡と、向こう数年の展望について話を聞いた。
ChatGPT登場1カ月後の決断

KDDI株式会社 経営戦略本部 Data&AI センター長 木村 塁氏
ChatGPT が2023年2月に日本でも大きな話題となった直後、KDDI では既に全社展開に向けた動きが始まっていた。当時の社長である髙橋誠氏が生成 AI の変化に強い関心を寄せ、トップダウンでの推進を決断する。わずか2カ月後の4月には、木村氏を中心とした横断組織の立ち上げが進んでいた。
もっとも、当時の ChatGPT 3.5は今と比べるとハルシネーション(誤情報生成)も激しく、使い方も手探りの状態だ。それでも着手を決めたのには明確な理由があった。
ーー当時はまだ技術的な課題も多かったと思いますが、何から取り組もうと考えたのでしょうか
木村:当時はコンシューマー向けにChatGPTがヒットしていて、翻訳ができるとか文章作成ができるといったところから始まりました。その中で成功事例の1つとして言われていたのがバックオフィス系の業務とカスタマーサポートです。このあたりがまず進めるべきポイントなのかなと思いながら着手しました。
経営戦略本部が旗を振り、トップダウンで進めるフォーカスエリアを決定。カスタマーサポート、購買経理業務、営業 DX、クリエイティブ制作を主要な取り組み領域として定めた。
当初は資料作成や議事録作成なども含まれていたが、その後の展開で方針を修正していく。Microsoft Outlook や Google カレンダーなどに AI 機能が組み込まれていくにつれ、自社であえて作る必要はないと判断。より本質的な領域に注力していった。
全社を巻き込む「3つの仕掛け」

トップダウンで方針は決まった。しかし大企業で全社展開を実現するには、現場の理解と協力が不可欠だ。木村氏らは意識改革のために3つの施策を実行する。
第一が生成 AI 活用コンテストの開催、第二が全社員を対象とした基礎講座の実施、そして第三が当時の社長である髙橋誠氏によるメッセージ発信だ。特に社長自らが全社員向けのタウンホールミーティングで生成 AI を軸にした会を開催したことは、組織に大きなインパクトを与えた。
ーー全社を巻き込むために、どのような工夫をされましたか
木村:コンテストを全社で開きました。当時はプロンプトエンジニアリングをみんな身につけましょうという風潮が強かったので、そのスキルを高めるのと、こういう使い方ができるという事例を知ってもらうことを含めて、全社コンテストを開いたのは大きかったです。
それと全社員が受講するような生成 AI の基礎講座もやりました。プロンプトエンジニアリングという言葉もみんな知らなかったと思いますし、「ハルシネーションが起きるものだよね」ということを知っている人も知らない人もいたので、そういうような前提知識をつけてもらえたというところで、だいぶ底上げできました。
ーートップのコミットメントも重要だったのでは
木村:当時の社長の髙橋が全社員向けに直接話をするタウンホールミーティングで、生成 AI を軸にした会を何回かやりました。現場でこういう使い方してるんだよとか、使わないともうこの先やっていけないよねみたいなメッセージを社長自らが発信したというのは、現場の社員もそうですし、経営に近いメンバーに対しても結構いい刺激になりましたね。我々の組織だけでは、そこまで強いメッセージ性はないので、トップがそういったメッセージを発信してくれたというのは大きかったです。
現場が見出した最適解
全社展開への号令はかかった。
しかし現場では当然、課題もあった。特にカスタマーサポートでの導入には慎重論が根強く、ハルシネーションのリスクを前に「お客様に対して100%の精度で」という声が上がる。しかし、それは不可能だと木村氏らはわかっていた。
ターニングポイントとなったのは、現場自身が適切な使い方を見出したことだ。
完全に0から回答するのではなく、お客様の発言内容がわかりにくかったら聞き返す AI にする。あるいは長すぎるチャットを要約してくれるチャットボットにする。ハルシネーションのリスクが基本的にない入れ方を、現場が見つけていった。
ーー現場での不安は
木村:もちろんありました。ハルシネーションのリスクがかなりあったので、カスタマーサポートの中でどこまで導入するかは結構議論になりました。100%の精度でみたいなことを言い始めるんですけど、それは不可能だとわかっているので、どこで折り合いつけるかとか、どういう形で入れるかが超えなければいけない壁でした。
ーーそれをどう乗り越えたのでしょうか
木村:カスタマーサポートでも、完全にお客さんに対して0から回答するのではなくて、お客さんの発言がわかりにくかったら聞き返すような AI にしたり、チャットで長文を書いてしまって従来のチャットボットだと何を回答していいかわからなかったものを、これですかねって要約してくれるようなチャットボットにしたり。
そうするとハルシネーションのリスクは基本的にはないのですが、そういった入れ方を現場自身で見つけながら導入してくれたのが1つターニングポイントになりました。

購買経理業務でも同様のアプローチが功を奏した。すべてをチェックするのを AI に任せるのではなく、ダブルチェックの片方を AI にやらせることで工数を半分に減らす。人間がチェックすべきところとそうでないところを見極める。それぞれのユースケースで現場が考えてくれたことが大きかった。
木村氏の技術の進化に対する考え方は明確だ。
日々進化することはわかっている。だから今できなくても別にいい。それよりも現場での使いこなし、ユースケースに合わせた役割分担を考えられるようになることの方が重要だと考えていた。
この「現場との対話」を実現するため、木村氏は開発チームと現場の連携を重視する。
ーー技術的なブレイクスルーよりも、現場の使いこなしが重要だったのか
木村:技術的なところに関しては、日々進化することはもうわかっていたので、今はできなくても別にいいやと。
技術的なところで大きなターニングポイントがあったというよりも、やっぱり現場での使いこなしですね。そのユースケースに合わせて、人がやるべきところと今の AI 技術でここまでしかできないけどここまで任せようとか、そこの役割分担を自分たちで考えられるように現場も含めてなったというのが大きなターニングポイントでした。
最初は技術的な見解も違って対立しがちだったが、ワンチームでやるようにしていく。技術側が現場のどういう業務で回っているかをきちんと理解し、現場側も AI に対しての知識を深める。両方が合わさったことが、壁を越えた要因だった。
次に続く:1万人組織に生成AIをインストールする方法(後編)——年間2.4万時間削減、スタートアップとの役割分担
関連リンク
関連記事
-

「AI レディ化に投資する」——変わり始めた日本企業
2026年02月19日
-

ワークフローが美しい国だから必ず勝てる——フライウィール横山直人氏が語る、AI 時代の日本企業の勝ち筋
2026年02月17日
インタビューの記事
-

世界を構造化するビデオインテリジェンスの旗手 - インフィニマインド
2026年03月05日
-

日本発、クリエイターエコノミーで産業変革を目指す - BitStar
2026年03月04日