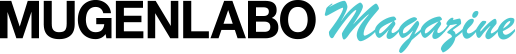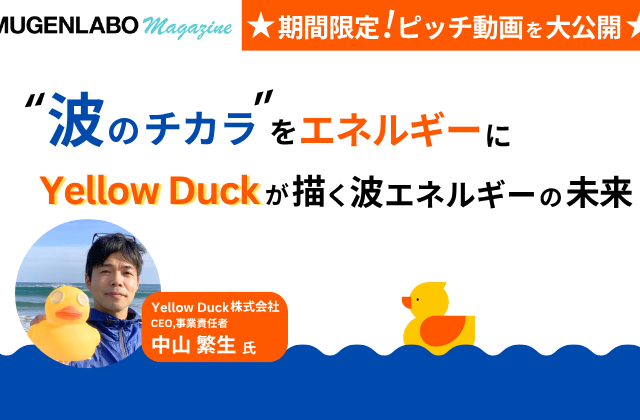- インタビュー
2025年01月31日
米国発の抹茶革命——CUZEN MATCHAが目指す、日本の伝統と新しい価値の循環

- World Matcha
塚田 英次郎 - 代表取締役CEO
サントリー在籍時代に「特茶」のヒットを生み出し、スタンフォードMBAで起業家精神を培った塚田英次郎氏。2014年頃からアメリカで広がり始めた抹茶カルチャーに着目し、World Matchaを創業。独自開発した抹茶マシンと厳選された日本産抹茶で、コーヒーに代わる新たな選択肢として世界20カ国以上で展開中です。
日本の伝統産業と世界の新しいライフスタイルを繋ぎ、持続可能な価値の循環を目指す挑戦に迫ります。
抹茶×テクノロジーで切り開く新市場

CUZEN MATCHAが提供する抹茶マシン
元々アメリカではコーヒーのカフェインがきついという声が増えてきていました。特に午後や夜は飲めないという方が多く、その代替飲料として抹茶が注目されるようになってきたのです。
塚田氏
CUZEN MATCHAは、抹茶を作るマシンの開発・生産・販売と、厳選したオーガニックの抹茶茶葉の供給を手がけています。同ブランドの特徴は、エスプレッソマシンのように誰でも簡単に本格的な抹茶を淹れることのできる独自のシステムを開発したことにあります。
抹茶には、高い栄養価や抗酸化作用があることが知られています。茶葉を丸ごと摂取できることから、ハリウッドセレブの間でも人気を集めているといいます。
以前はザクロやブルーベリーなどのスーパーフードが注目されていましたが、抹茶の方が抗酸化力が高いことがわかってきました。サプリメントに近い健康効果を、飲み物として楽しめるのです。
塚田氏
同社のマシンは、当初は家庭用として開発されました。コロナ禍でのパンデミック中に発売され、Kickstarterでの資金調達にも成功。その後、実際に使用したユーザーからの声をもとに、カフェなど業務用のニーズにも応えるべく製品ラインナップを拡大しています。
日本の生産者から良質な抹茶を適正な価格で仕入れ、それを世界の消費者に提供する。その結果、生産者にも適正な対価が還元される。このような循環を作り出したいと考えています。
塚田氏
日本国内では、お茶の消費量が減少し、ペットボトル飲料へのシフトが進む中で、原料茶葉の価格競争が激化。生産者への価格圧力が強まっている現状に対し、新たな活路を見出そうとしているのです。
サントリーからシリコンバレーへ

World Matcha 代表取締役CEO 塚田英次郎氏
塚田氏の起業家としての道のりは、サントリーでの経験が起点となっています。
大企業でそれなりの期間を過ごし、結果も出せていました。特に特茶の開発では大きな成果を上げることができ、それが次のステップに進む自信にもなりました。
塚田氏
しかし、組織の中での限界も感じていたといいます。転機となったのは、サントリーの支援を受けてのスタンフォードMBA留学でした。
スタンフォードでは、企業家が非常にリスペクトされています。大企業での経験も評価されますが、それ以上にチャレンジ精神が重要視される。そこで学んだ起業家としての考え方や、エクイティを活用した資金調達の方法など、日本では一般的ではない事業展開の手法を知ることができました。
塚田氏
留学時の2006年当時、アメリカでは日本茶を飲む人はほとんどいませんでしたが、2014年頃から若い世代を中心に抹茶を飲む文化が広がり始めます。
クラスメイトに日本茶を飲んでもらうと、みんな苦くて飲めない、砂糖や蜂蜜を入れないと飲めないと言っていた。それが10年後には、濃い抹茶を好んで飲むようになっている。この変化に、大きな可能性を感じました。
塚田氏
帰国後、サントリー内で新規事業として抹茶プロジェクトを立ち上げ、社内ベンチャーとして展開。しかし、より大きな可能性を追求するために、独立を決意します。
グローバルに広がる抹茶カルチャー

抹茶マシン利用イメージ
抹茶文化のグローバルな広がりは、地域によって異なる様相を見せています。
2022年の夏にヨーロッパを訪れた際は、まだ抹茶文化が浸透していないと感じました。当時、ニューヨークやロサンゼルスには既に抹茶専門店があり、アメリカはヨーロッパに比べて5、6年先を行っているような印象でした。
塚田氏
しかし、その状況は急速に変化しています。2024年5月にパリで開催されたVivaTechというテックイベントに出展した際には、現地の人々の抹茶への理解が深まっていることを実感したといいます。
パリの人々は抹茶のテイスティングの作法を心得ていて、香りを確かめ、味わいを楽しむ。フランスは私たちの製品と非常に相性が良いマーケットだと感じました。
塚田氏
東南アジアでも抹茶人気は高まっています。タイやシンガポールでも抹茶文化が広がりを見せており、興味深いことに、日本以外のほぼ全ての国で抹茶が流行しているという状況が生まれています。
日本では歴史的に、抹茶は一部の層に限られた高価な飲み物でした。江戸時代に、誰でも気軽に日常的に飲めるようにと煎茶の製法が開発され、それが広く普及しました。その流れを汲んで、現代では多くの日本人が煎茶やペットボトルのお茶を好んで飲んでいます。
塚田氏
一方で、日本以外の国々では、日常的な煎茶文化が根付いていなかったからこそ、新しい選択肢として抹茶が受け入れられているといいます。
また、インバウンド観光客の間でも抹茶は人気を集めています。渋谷などの観光地では、外国人観光客向けの抹茶カフェが増加しており、日本の伝統文化への関心の高さを示しています。
事業成長の要は、人との縁

抹茶マシンで抽出した抹茶
CUZEN MATCHAの成長戦略の特徴は、人との繋がりを重視した事業展開にあります。
昭和的かもしれませんが、人との縁を大切にしています。時には泥臭いことをやることもありますが、その中に非常にパワフルな人々との出会いがあります。
塚田氏
特に印象的なのは、製品に共感した顧客が自発的に応援者となっていく様子です。「これはいいから、もっと広がっていかないといけない」と考えてくれる人が、特にアメリカには多くいるといいます。そのため塚田氏は、積極的に移動して人々と出会うことを重視しています。
投資家との関係構築においても、独自の哲学を持っています。
私のような超ニッチな領域で、しかも伝統的な分野に挑戦する事業には、それを理解し、応援してくれる投資家が必要です。金額の大小に関わらず、私たちのビジョンに共感してくれる方々と共に歩んでいきたいと考えています。
塚田氏
アメリカを拠点としながら、日本にも拠点を持つハイブリッドな事業展開も特徴的です。現在では20カ国以上にEコマースで製品を展開していますが、これは意図的な戦略というよりも、世界中に抹茶を求める顧客が自然と存在していることの表れだといいます。
私たちのステージとしては少し早いかもしれないほど事業を手がけるエリアが広がっていますが、それは無理をして実現したわけではありません。世界中にこの製品を求めるお客様がいて、今ならそれに応えることができる。その結果として、自然な形で事業が拡大しているのです。
塚田氏
日本の伝統と世界を繋ぐビジョン
CUZEN MATCHAの挑戦は、単なる抹茶製品の販売にとどまりません。インバウンド観光との連携も今後の重要な展開の一つです。
私たちの製品を愛用してくださるお客様は、どういう環境で抹茶が作られているのか、より特別な体験をしたいと考えています。そこで、茶畑への訪問など、体験型コンテンツの提供も考えています。
世界中から日本に来てくださるお客様に、本物の抹茶体験を提供し、本国に戻ってからも継続的に製品を購入していただく。そうした有機的な繋がりを作っていきたいです。
塚田氏
CUZEN MATCHAの挑戦は、日本の伝統産業に新しい可能性を見出し、グローバルな価値創造へと昇華させようとする試みといえるでしょう。抹茶という日本の伝統文化を、現代のテクノロジーと結びつけることで、持続可能な形で世界に広げていく。その取り組みは、まさに始まったばかりです。
関連リンク
関連記事
インタビューの記事
-

MUGENLABO UNIVERSEから生まれた新たな教育の形 ― ライフイズテックとアストロスケールが描く「宇宙×デジタル」の未来
2026年02月10日
-

素材の力で未来を創る - マテリアルゲート
2026年02月03日