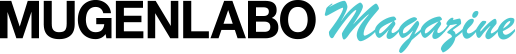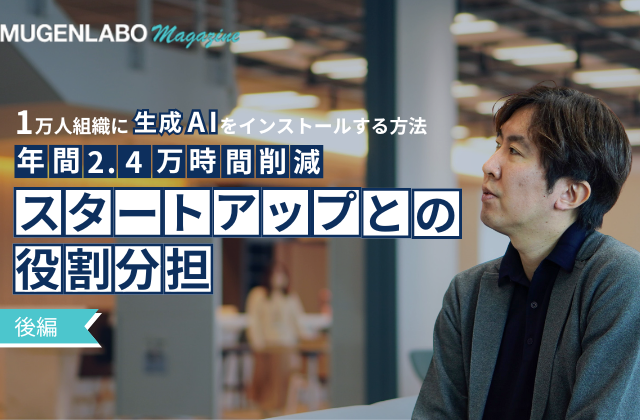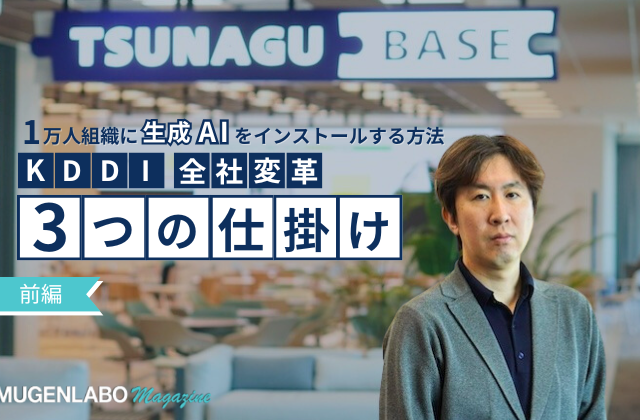- インタビュー
2025年10月28日
子どものスマホ利用を守れ!KDDIがU12プランに異例のスタートアップ「Adora」抜擢——その舞台裏を聞いた

- Adora株式会社
冨田 直人 - 代表取締役
- KDDI株式会社
丸岡 孝至 - パーソナル事業本部サービス 商品本部サービス開発部
- KDDI株式会社
小河原 晃子 - パーソナル事業本部サービス 商品本部サービス開発部
2025年9月、KDDIは新たな子ども向け料金プラン「U12バリュープラン」の提供を開始した。注目すべきは、このプランにバンドルされたサービス「コドマモ」が、創業わずか2年のスタートアップ Adoraが開発したものだ、ということだ。愛知県警からの相談を受けて藤田医科大学で開発が始まり、産学官連携で生まれたこのサービスが、なぜ KDDI の料金プランに組み込まれることになったのか。Adora 代表取締役の冨田直人氏と、KDDI でサービス開発を担当する丸岡孝至氏、小河原晃子氏に話を聞いた。
KDDIでのスタートアップ連携事例——料金プランバンドルという「異例中の異例」

KDDI∞Labo 第6期デモデイの発表会の様子
デモデイを契機として、KDDI とスタートアップの協業へも複数進展
KDDI とスタートアップの連携にはあるパターンが存在していた。
そのひとつが、2011年に開始したインキュベーションプログラム「KDDI∞Labo」で採択された企業が、auスマートパス(現在は Pontaパスに改称)でサービス連携に至るというルートだ。
ソーシャルギフトサービス「ギフティ」はその代表例だろう。2011年の KDDI ∞ Labo 1期で採択され、2012年に KDDI Open Innovation Fund(以下:KOIF) から出資を受けた後、同年8月には「giftee for auスマートパス」として月1回ファミリーマート利用券を友だちに贈れる特典を提供開始。
創業わずかのスタートアップにとってこの「auスマートパス」連携はユーザー獲得のみならず、信用の担保という点でもメリットが大きかった。ギフティ以外のプログラム採択社はこの「auスマートパス」連携を目指し、自然とここがスタートアップと KDDI の「連携ショーケース」となっていた。
その後、この取り組みやカルチャーは現在も KDDI ∞ Labo や KOIF からの出資といった形で継続している。例えば新社屋となった「TAKANAWA GATEWAY CITY」の THE LINKPILLAR 1 NORTH に設置されているローソンでは、「Real×Tech LAWSON」の取り組みが現在進行形だ。
KOIF 支援先の店内飲料品出しロボット(Telexistence)、サイネージを活用した顧客属性解析・商品レコメンド(Idein)、防犯カメラ映像解析による店舗運営効率化システム(韓・Deeping Source)などのサービスが実際の検証・商用ベースで稼働している。一方、私たちが普段目にする通信サービスは話が異なる。
数千万人の顧客基盤をベースとした「料金プラン」に組み込まれるのは、Netflix や Apple Music など大手のサービス連携が中心で、創業わずかのスタートアップサービスが採用されるケースは稀なのだ。
子どもの安全を守れ——サービス検討と Adora の出会い

KDDI株式会社 パーソナル事業本部サービス 商品本部サービス開発部 小河原 晃子氏
今、子どもを取り巻くインターネット・スマートフォンの環境は難題に向き合っている状況にある。例えばオーストラリアでは、16歳以下の SNS 利用禁止を打ち出すなど、特に欧州を中心に規制の声が広がっている。
コドマモに出会った経緯を教えてください
こうした背景もあり、KDDI では青少年が安心して利用できる環境を充実させようという動きがあった。それを担当しているのが小河原氏の企画チームだった。
もともとサービス開発部では、青少年向けのフィルタリングサービスを担当していました。昨今の青少年のスマートフォン利用を取り巻く事件や課題を受け、フィルタリング以外の機能、特に SNS を安全に利用できるようにするにはどのようなニーズがあるのか調査しているなかで、Adora さんの「コドマモ」というサービスを見つけたんです。SNS の利用を制限するのではなく、どうしたら親も子も安心してSNSを利用できるのか。そういった観点でサービスを作られているところや、 AI を活用した画像検知など、これまで KDDI で提供できていなかった多くの技術・機能をお持ちであることに魅力を感じました。
小河原氏
コドマモは、子どもが安心してスマートフォンを利用するために提供されるフィルタリングサービスの一種になる。通常、KDDI をはじめ各キャリアが提供するフィルタリングサービスは、有害サイトやアプリのカテゴリ遮断、利用時間制限といった「ネットの通行管理」が中心で、法令によって義務付けられているのが特徴だ。
一方、コドマモはそのアプローチが根本的に異なる。それが AI による「内容検知」だ。例えば、自分の子どもがチャットアプリで友人とコミュニケーションを取るとしよう。従来のフィルタリングの考え方ではこれそのものを制限してしまう。しかし、コドマモは知らない相手との不審チャットや、わいせつ画像の撮影を AI がリアルタイムで検知し保護者に通知する。
つまり、インターネットを正しく使えるよう、保護者がサポートできる仕組みを提供しているのだ。なぜこのようなコンセプトが生まれたのか?それはコドマモが生まれた背景を紐解くことで見えてくる。
学生起業から掴んだチャンス

Adora株式会社 冨田 直人氏
コドマモを開発する Adora は、2023年7月にスタートアップした。代表取締役の冨田直人氏は慶應義塾大学在学中に学生起業した会社を株式譲渡したのち、東京工業大学大学院の在学中に同社を起業した28歳だ。現在、Adora ではインド系の開発メンバーが多数在籍しているが、彼らは冨田氏が過去にインドに長期滞在した際のつながりからだそうだ。
コドマモの開発経緯はあるひょんなきっかけから始まる。
冨田氏は藤田医科大学の客員教員としての顔も持っているのだが、そこにある日、愛知県警から一通の相談が届く。当時、子どもたちのSNS利用課題が顕在化する中、開発力があると噂になっていた冨田氏にその課題解決の白羽の矢が立ったのだ。
改めてコドマモを開発した経緯を教えていただけますか?
2021年秋に愛知県警がSNS性被害防止の対策について、起業家を育成するプロジェクト団体「Tongali」に相談しました。参画している藤田医科大学が名乗りをあげ、同学の産官学連携推進センターの村川修一准教授や、客員教員の私、そして愛知県警を中心に、上記の社会課題を解決するためにプロジェクトが始まりました。
冨田氏
こうして生まれたのが、AI 検知を活用した新たなコンセプトのコドマモだった。利用を制限するのではなく「見守る」アイデアが受け入れられ、単体のスマートフォンアプリとして利用を伸ばしていった。
さらにこの「AIによる危険検知」というコンセプトはアプリに閉じる必要はない。今年9月には愛知県日進市で、約1万人が利用するGIGA端末に不適切画像の検知機能を備えた「コドマモ for School」を導入。同市と Adora は学校現場のICT活用に関する連携協定を締結している。冨田氏に改めてこのコンセプトについて聞いた。
制限ではなく利用させるというコンセプトはどのようにして辿り着きましたか?
個人的に、中学生の時からスマートフォンを使っていたので、スマートフォンやインターネット自体にすごく愛着があるんです。
結局のところ、みんな使う流れになっていくのは不可逆的だと思うんです。スマホ制限とかの話題も出てきていますけど、使いながら使い方を覚えていく方が、よっぽど本質的だと考えています。
冨田氏
コドマモ自体の立ち上げで愛知県警などと協議する中、どういった話し合いがあったんですか?
警察の方々も闇雲に「スマホを使うのはやめましょう」みたいなことを言っているわけではなく、「スマホを利用することを前提にして、制限によって安全を守りつつも、コドマモもサービスとして現実的に使いやすくしないといけないよね」というユーザビリティの必要性についての話し合いなどがありました。結局使ってもらえないと、守れるものも守れないので、ユーザービリティを確保しつつ、使っていただきながらリテラシーの向上を促せるサービスにしたいという考えに至りました。
冨田氏
こうして既存のフィルタリングサービスとは全く異なるアプローチに成功していたコドマモ。一目でその可能性に気がついた小河原氏たちはその後、Adora とのつながりを探すことになる。そのきっかけを作ったのがスタートアップ投資を手がける KDDI∞Laboだった。KDDI∞Laboを担当する木村氏から紹介を受けた小河原氏は冨田氏と出会い、採用に向けた協議を開始する。
コドマモ同様のサービスは多数存在したが、AIによるSNS検知や危険画像検知、お子さまの位置情報検知などを網羅的にカバーするものは少なく、国内だと最もクオリティが高いことを確認した。また競合製品の多くは海外ベンダーでありビジネス連携や開発面での懸念もあり、コドマモとの連携が魅力的に映った。しかし相手は創業からわずか2年のスタートアップだ。

すぐに採用とはならなかった?
青少年向けのあんしんフィルターはもともと無料のサービスなので、そこにプラスで価値をつけて有料にするところがなかなか事業として成立しなかったというのが、当時の検討結果でした。我々のあんしんフィルターを利用してくれているお客さまのうち、何割ぐらいがコドマモを有償で使ってくれるのだろうかと仮定して試算するとどうしても厳しい状況でした。
あんしんフィルターのサービスの一部であれば、店頭で案内することが法令で決まっているので、ちゃんと案内していただけるものの、これが通常のバンドルサービスだとそうはいかないんです。それで、あんしんフィルターの一部の機能として、このコドマモの機能を SDK 化して提供していただけないか、という話をしました。ただ、そこはコドマモのコンセプトとして難しいというお話でした。
小河原氏
子どもたちに安心してスマートフォン・インターネットを使ってもらうためにコドマモはぴったりのサービスだった。しかし、これを単体で販売する「事業」として成立させるのはハードルが高い。そして誰もが想像するであろう件、それが「自社開発」という方法だ。開発チームはなぜ、スタートアップの力を借りようとしたのだろうか。
ハードルが高いと分かって自社での開発は検討しなかった?
一応、そういった話はしたものの、やはりイチからその機能を作っていく形になるので、スピード感が遅くなるということと、我々にコドマモ的なアプローチの知見がないので同じ水準のものを作れるかというと難しいかなと思いました。
小河原氏
技術力については頑張ればなんとかならなくもないのですが、やはりそもそものコンセプトや考え方が違ったんですね。従前から提供していた青少年フィルタリングは基本的にネット利用を制限をするものですが、コドマモは自由に使っていただいたうえで危険を通知するというものです。新しいコンセプトの単体商品の提供を目的に一から自社でアプリ開発するところまでは、我々の力不足もあり踏み込めませんでした。
丸岡氏
コドマモ採用を断念しそうになっていたその時、小河原氏たちチームに朗報が舞い込む。それが新たな料金プランの新設プロジェクトだった。
1年がかりのプロジェクト、頓挫の危機を乗り越え採用へ

2025年9月1日に提供開始されたKDDIの「U12バリュープラン」は、5~12歳を対象とした子ども向け料金プランだ。送受信最大300kbpsの通信速度に制限されているのが特徴で、動画サービスなど大容量のコンテンツは自然と制限される。
そしてこの料金プランのプロジェクトがコドマモ採用への大きな追い風となった。
料金プランの新設はやはり大きかった?
はい。料金プランとセット化された機能として提供するのか、料金プランとは切り離した単体機能として提供するのかでは、全社的なマーケティングもショップ等店頭スタッフの皆さまによるお客さまへのご案内活動もその注力度合いが大きく差が出ます。良い商品を最大限お客さまに認知してご利用いただくためには、料金プランに包含されるかどうかは非常に重要なポイントとなります。
丸岡氏
全社のマーケティング戦略で若年層向けの料金プランを検討している中、小学生層(U12)は子どものスマホ利用に対する親の不安が高く、安心要素を重視していることは調査でわかっていました。他の安心サービスとも比較した結果、ワンパッケージで保護者のニーズや社会課題を解決できるサービスであるコドマモが最適という結論に至りました。
小河原氏
スタートアップ側としてこの話がきた時、不安はなかったですか?
せっかくいただいたお話を無駄にしてしまうとよくないと思っていたので、結構緊張感がありました。普通のリリースとは違って、KDDI さんというブランドがあるので、我々が単独でバグを出すのとでは発生する問題の大きさが違う。
これまではFacebookのザッカーバーグ的な「Done is better than perfect」みたいな思想で、とりあえず作って出そうという感じでやってきたんですが、これではいけないなと。やはり責任感というものを強く感じました。
冨田氏

Adora株式会社 冨田 直人氏
KDDI株式会社 パーソナル事業本部サービス 商品本部サービス開発部 丸岡 孝至氏
社内で料金プランの検討は長引いたものの、開始から半年ほど経過してようやく Adora にバンドル推進の連絡が届く。
創業2年というスタートアップのサービスが採用に至った最後の決め手は、アイデアだけに終わらない利用実績に加え、企画チームが奔走した数々の社内調整にあった。
最も気になるのが創業からわずかのスタートアップサービスをどうやって社内説明したのか、という点です。どういう点が論点になりましたか?
コドマモは既にサービスとして世に出ており、私も小河原さんもそのサービスを実際に利用したうえでその良さをリアルに説明できたことは大きかったです。これから作るサービスです、となると社内でも「ホントにそんなに良いものなのか?」となりますが、実際にモノを見て使って触っていますので自信をもって説明できました。
丸岡氏
一方で、現在のコドマモにはフィルタリングサービスの要件を満たす機能(WEB・アプリフィルタリング)がないため、店頭では「あんしんフィルター」やOSのフィルタリング機能を合わせてご案内する必要があったんです。
U12向けのフィルタリングサービスをコドマモのワンパッケージですべて完結できていないという点や、お子さまを守るコンセプトのすみ分けについて、丁寧に社内説明をしましたし、時間を要しましたね。
小河原氏
与信という点も気になるところです。大手企業ではそもそも取引する企業に与信審査をかけますよね
今回、かなり多くのお客さまがご利用になる料金プランに入るということで、万が一、このサービスが途中で終了となった場合はどうするのか、何か障害があった時のサポート体制は何人ぐらいで24時間365日対応してくれるのか等、そういったところを Adora さんとお話ししながら、社内でご了解いただける水準まで整えていきました。
小河原氏
創業間もないスタートアップだと、そもそもお取引をすること自体のハードルが高いと思います。だからこそ「ここがベストなんです」と社内で納得いただく必要がありました。商品力があったということが一番大きかったです。
丸岡氏
他社製品の比較なども事前にしましたし、いろいろ調べてもらったおかげで、その辺りの説得力は確保できました。
小河原氏

もう一点、今回コドマモはあくまで「Adora」のサービスとして料金プランに組み込まれることになった。つまり位置付けとしては Netflix や Apple Music などと同じ独立性を保ったサービスだ。
一方、利用者としては U12バリュープランを契約すれば、通常790円かかる利用料を個別に支払う必要はない。つまり au/KDDI のオリジナルサービスのような体験になっている。
この「絶妙な立ち位置」を作ったことが、結果的に連携をうまく着地させたようだ。それは連携に当たっての開発内容にも現れている。
今回のバンドルに当たってサービスそのものを改修する必要はどの程度あったのでしょうか?
改修については、本来は有償のプランであるコドマモを「au ID」で無償で使えるようにするという認証関連の開発がありましたが、基本的にはそれだけでした。
小河原氏
どれくらいの期間で開発が完了したのでしょうか
これ自体は3ヶ月ぐらいだったと思います。その前に、仕様の理解をしていただくために、あらかじめドキュメントを参照いただいたり、au IDを実装いただくための様々な手続きを予め進めていました。そういったものが揃った上で、開発期間として3ヶ月ぐらいです。
小河原氏
アプリをau仕様に改修してau版コドマモを提供するという方向性もあり得たわけですが、個別カスタマイズは開発期間もかかりAdora様の開発体力の観点からも望ましくないと判断しました。
当社カスタマイズのためにかける工数が拡大すると、Adora様が本来割くことができたはずのコドマモそのものの機能強化やUX改善のスピードを毀損することとなりお客さまへの提供価値を損ねると考えたからです。結果として、au ID実装に係る開発を3ヶ月という短期間で完了いただくことができました。
丸岡氏
冨田氏たちが改修にあたって特に意識した点は?
アプリは端末に結構依存するところがあって、どんな端末なのか、どんなOSなのかという、いろんな環境があるんですね。KDDI さんの場合、そのいろんな環境がある中で、ちゃんとテストに時間を割く必要があるということが、最初の段階ではできていなかったんです。
実際にリリースするまでの段階ではそこに対しての考え方だったり、テストする体制だったりを大幅にアップデートする必要が出てきました。当たり前といえば当たり前かもしれないですが、ただ「頑張ろう」というだけでは難しくて。
「バグがあっても使いやすいものだったら受け入れられるだろう」みたいな思想でやってきたスタートアップにとって、急に「ちゃんと丁寧にやらなきゃ」と思っても、なかなか急には変えられないんですよね。そこは苦労しましたし、かなり意識して取り組みました。
冨田氏
au ブランドのサービスではないとしても、一定基準のサービス提供レベルがあると思います。この辺りの検証はどのような形で取られたのでしょうか
弊社のさまざまな自社アプリの開発を行っているアプリケーション開発部という部門があります。同部門と連携し、また同部門からの紹介でKDDIテクノロジー社という様々なアプリ評価を実施いただく実績のある関連会社の協力もいただきました。
KDDIテクノロジーには、KDDI で発売している端末と現在使われているOSバージョン(Android/iOS) の組み合わせで網羅的に検証をお願いしました。
また今回新規開発した au ID連携部分については、料金プランの変更等でau IDの契約ステータスが変わったとき、au ID を統合した時、料金プランを解約した時など、あらゆる契約パターンの試験を当然のことながら確認しています。
小河原氏
単純なアプリの動作だけじゃなくて、キャリアならではの検証である。もちろん全てがスッキリといったわけではない。例えば法令で決められたフィルタリングサービスとの使い分けだ。ユーザーからするとどちらも子どもに安心してインターネットを使ってもらうための機能になる。ここが分かれていることで契約時の説明に一手間かかることになる。
自社サービスではないので、お客さまからの問い合わせに関わる役割分担をしっかりと整理しました。ベーシックな使い方や au ID に関わるところはKDDI 側で回答する。それ以外のサービスの詳細や細かい設定方法などはすべて Adora さんにお客さまサポートをお願いするという形で、お客さまにとってどのような対応が最も喜ばれるかを起点に、「こういう時はこちらに問い合わせしてください」と社内で周知しました。
小河原氏
こうして様々なハードルを乗り越えたスタートアップ・サービスは無事、新たな料金プランのパートナーとして、その公開日を迎えることになった。
子どもたちのインターネットを安心に導く

コドマモの技術的な特徴は、オンデバイス検知にある。従来のフィルタリングサービスが事後的に制限をかけるのに対し、コドマモは端末内でリアルタイムに解析を行い、危険を事前に察知して通知する仕組みを採用している。プライバシー保護の点でも端末側でさまざまな情報を扱えるのはメリットだ。
このアイデアを大手の開発力で実現することはできるはずだ。しかし、サービスインという様々な要件に照らし合わせた時、スタートアップとの協業は大きな選択肢になる。今回のケースはそれが事業の飛び地ではなく「本丸」でも可能であることを示してくれた。
子どもにとってのインターネット利用をどのように導くのか?この大きな難題こそが大手とスタートアップという立場の違いを乗り越える大きな原動力になっていたように思う。インタビューの終わり、協業を開始したそれぞれに今後の子どものインターネット・スマートフォン環境のあるべき姿について尋ねた。
すごく嫌だと感じられるものは、サステナブルじゃないと思うんです。理論的には「こういうふうに制限した方がいい」というのはあるんですが、その落としどころを見つけることが重要です。リテラシーを高めて自分で学んでほしいという思いと、実際問題として守らなければいけない部分とのバランスですね。
例えば、子どもに「自分で考えてほしいから、何か変なものが来ても自分で判断しようね」と言っても、危険かどうかを判断する力は一朝一夕には身につかない。そこは親御さんと一緒に考えてもらう必要があるし、制限が必要な部分もどうしてもある。このトレードオフをどう解決するかが、すごく難しいところです。
だからこそ対話が重要だと思っています。ユーザーが実際に使ってくれるのを分析しながら、本質的に何が子どもにとっていいのか、何が保護者にとっていいのかを考えながらユーザー体験を設計することが、一般的なサービスよりももっと求められると思うんです。
実際にユーザーインタビューをしていると「忙しすぎて仕事もしていて、なかなか子どもとの対話ができない。子育てがオペレーションのようになってしまって、子どもが何を感じているのか、どんな悩みを持っているのかを汲んであげることが、現実問題として難しくてできていない」といった声を耳にします。
それを解決できる、対話のきっかけになる、子どもの気持ちを汲んであげられる助けになれるようなサービスになるべきだし、そのポテンシャルがあると思っています。
冨田氏
従来のペアレンタルコントロールアプリは「使わせない」「制限する」というアプローチですが、もはや老若男女でネットの利用は当たり前になっています。
お子さまがネットを使うことで悪影響が出るとの論調や議論がありますが、どのようにすればネットと共存していけるか、ネットをいかに「正しく」使いこなしていけるか、その観点でのネットリテラシが問われていると考えており、そのような課題解決をこれからも Adora さんと一緒にお客さまにご提案していきたいと思っています。
小河原氏
AdoraとKDDIがマッチングした背景

KDDI∞Laboでスタートアップと大企業との事業連携の推進を担当しております。実は、今回の連携のきっかけは2年前に私がAdoraさんを小河原さんへご紹介したことでした。
毎週木曜朝に開催されているモーニングピッチでAdoraさんと初めてお会いし、KDDIとのシナジーを感じたことから、社内のアドレス帳であんしんフィルターの担当者を探し、小河原さんへチャットでご紹介させていただきました。当時はフィルターアプリの機能追加の予定がなく一度見送りとなりましたが、未成年向けスマホの新しいセキュリティサービス検討が始まったタイミングで、改めてお引き合わせをさせていただきました。
その後、社内でも多くの議論を経て、新サービスとしてリリースされるまで約1年半の歳月がかかりました。丸岡さん・小河原さん・Adoraさんとのいくつかの打合せにも参加させていただきましたが、皆様の「最後までやり切る」という強い想いが、今回の連携実現につながったと感じています。
今回の取り組みを通じて、toC向け通信事業の顧客価値向上に大きく貢献できたと実感しています。今後もスタートアップと事業部との連携を積極的に推進し、さらなる価値創出につなげていければと思います。
KDDI株式会社 SUグロース戦略部 木村朱里
関連リンク
関連記事
-

1万人組織に生成AIをインストールする方法(後編)——年間2.4万時間削減、スタートアップとの役割分担
2025年12月03日
-

1万人組織に生成AIをインストールする方法(前編)——KDDI、全社変革「3つの仕掛け」
2025年12月02日
インタビューの記事
-

ニッポン発、今ここにない未来をつくる - POCKET RD
2026年01月29日
-

レアル・マドリードのアクセラに採択 - AMATELUS
2026年01月28日