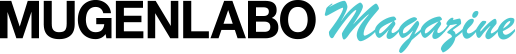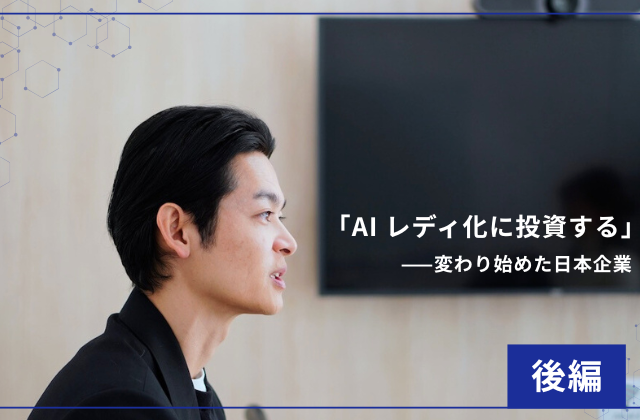- インタビュー
2025年04月08日
CES2025で大注目!ユカイなロボットたちの「なるほど」な役割とは
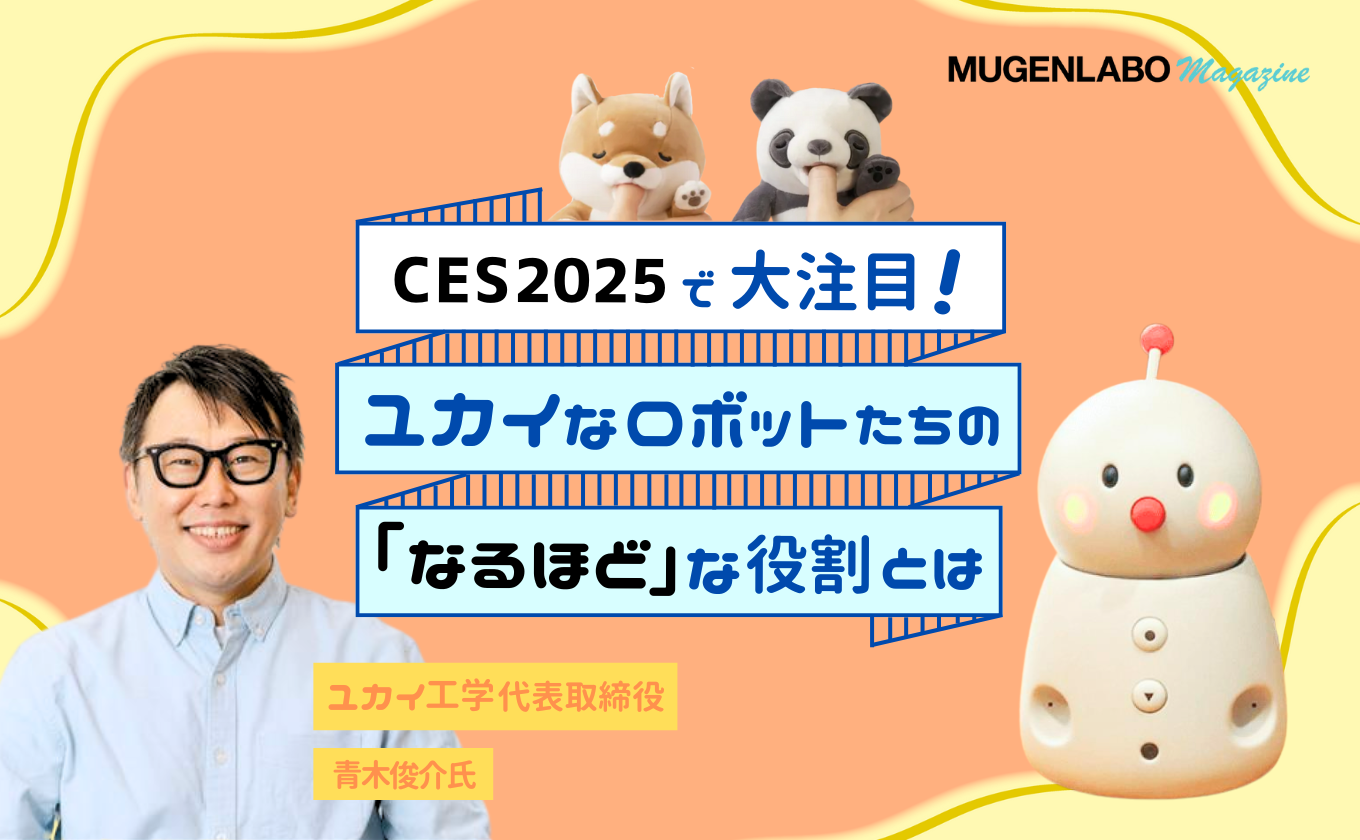
- ユカイ工学株式会社
青木 俊介 - CEO
1月に米ラスベガスで開催された国際的な電子機器の見本市「CES 2025」で大きな話題を呼んだ、ユカイ工学の新製品「猫舌ふーふー」と「みるみ」。海外メディアから絶賛され、セレブリティからも注目を集めた日本発のロボットの背景には「可愛さ」を武器にした独自の開発理念があります。
「ロボティクスで、世界をユカイに。」というビジョンを掲げるユカイ工学代表取締役・青木俊介氏に、CESでの反響、家庭向けロボットの可能性、そして世界展開の戦略についてお話を伺いました。
世界が認めた「ユカイなロボット」たち

こちらをチラ見してくる「みるみ」
ユカイ工学のロボットは、日本だけでなく世界からも高い評価を得ています。青木氏はCES 2025での反響について「すさまじかった」と手応えを語ります。
同イベントでユカイ工学は、新たに2つの製品を発表しました。1つは「猫舌ふーふー」という、熱い飲み物やスープを冷ましてくれる小型ロボット。もう1つは、「みるみ」というバッグに取り付け可能なチャーム型のロボットです。青木氏によれば、「どちらも非常に話題となり、InstagramやTikTokでは数百万再生を記録する動画が多数出現した」というほどの反響だったといいます。
さらに「Best of CES」という、テック系メディアが展示会で最も注目すべき製品を選出する企画では主要なテックメディアのベストにほぼすべて選出されたそうです。特にバッグチャームの「みるみ」は大きな話題となり、青木氏によるとパリス・ヒルトンもインスタで欲しいとコメントするなど、連日中国の投資家やバイヤーが途切れることなくブースを訪れるほどの盛況ぶりだったと言います。
実はユカイ工学の海外展開は、これまでもアジア圏を中心に着実に進められてきました。中国、香港、タイ、シンガポールなどでは、以前からディストリビューターがいたそうです。
高齢者向けのロボット製品も増えてきており、ヨーロッパの高齢者向けのディストリビューターとも提携して、販路を広げつつあります。
青木氏
アジア市場から展開を始めた理由について青木氏は、「可愛いものが好まれる文化があり、日本人と感覚がとても近いため」と説明します。国境を越えて愛されるユカイ工学のロボットたち。その背景には、「可愛さ」という感性に訴えかける製品開発の哲学がありました。
ロボットに「可愛さ」という武器を

製品試作プロセスの展示例(昨年開催の「DESIGNART TOKYO 2024」展示内容より)/同社リリースより
なぜ世界中で愛されるロボットを作ることができたのかについて、そのカギは「可愛さ」にあると青木氏は言います。
2011年に株式会社化したユカイ工学は、「ロボティクスで、世界をユカイに。」というビジョンを掲げ、家庭向けロボット領域を軸に事業を展開しています。青木氏によれば、家庭向けロボットの普及にはあるポイントが重要になるのだと言います。
家庭向けのロボットを製作する際、単なる利便性だけでは市場の拡大は難しいと考えています。可愛らしさや愛着を覚えるといった感情的な要素が非常に重要になるんです。
青木氏
そしてこの「可愛さならGoogleに勝てる」という発想が、ユカイ工学のユニークなアプローチを形作っています。テック業界の巨人たちにも負けない独自性を追求するこの戦略は、「もこもこした質感」や「思わず触れたくなるデザイン」といった特徴を持つプロダクト群として結実しています。
ユカイ工学のロボット開発のプロセスの特徴として、「全員で企画を出し、試作を繰り返す中で、商品化できそうなものをリリースする」方法があるそうです。この全社員参加型のアイデア創出文化が、独創的なプロダクトを生み出す土壌となっています。
この手法は「メイカソン」として体系化され、社内で定期的に実施されています。社員たちの自由な発想から生まれたアイデアは、迅速に試作され、実験を重ねる中で洗練されていきます。
家庭向けロボットの市場において「iPhoneのように市場のデファクトスタンダードになるようなプロダクトはまだ登場していない」と語る青木氏。その未開拓の領域で、ユカイ工学は可愛らしさと愛着を武器に、新たな扉を開こうとしています。
ロボットの「なるほど」な役割

赤ちゃんのように指を甘噛みしてくる「甘噛みハムハム」
青木氏が描く家庭内ロボットの未来図は、人間の弱点を補うパートナーとしての姿です。
青木氏は、現在のロボットたちの技術的進化を「AIがかなり発展していて、十分会話ができるレベル」と語ります。さらに「家の中にも多くのセンサーが設置され、IoT化が進むことで人間の行動をかなりの精度で把握できるようになっている」状況なのだそうです。
そうした技術進化を背景に、青木氏はロボットの出番を次のように語ります。
人間が最も苦手とするのは、何かを継続することです。人間の弱点にこそ、ロボットの出番があると考えています。ダイエットや英会話の学習といった継続が難しい、人間が苦手なことをサポートするという役割こそ、ロボットならではの価値ではないでしょうか。
青木氏
もうひとつ、人間のコミュニケーションが難しくなる場面もロボットの出番です。
例えば「今日は燃えるゴミの日です」とスピーカーから声掛けしてくれるリマインダー機能を持つロボットがいることで、「この通知のおかげで夫婦間の口論が減少した」というフィードバックもあったそうです。これは、夫婦間での日々のゴミ出しリマインドが非難のメッセージになりがちな問題を解消する効果がある、というわけです。
AIやIoT技術の進化とともに、ロボットは単なる機械から人間の行動や感情を理解し、適切なタイミングでサポートする存在へと進化しつつあります。
青木氏が描く未来では、ロボットとのコミュニケーションにより、人の生活がより豊かでスムーズになる可能性が広がっているのです。
注目の新製品と今後の展望

あついものも人間の代わりにふーふーしてくれる「猫舌ふーふー」
CES 2025で大きな話題となった2つの新製品「猫舌ふーふー」と「みるみ」は、同社のユニークな発想とデザイン哲学を象徴する存在となりました。
猫舌ふーふーは、食器のフチにつかまって熱い食べものや飲みものを「ふーふー」して冷ましてくれる小さなロボットです。開発背景には、子育て中の家族にとって、まだ熱いものが食べられない子どものために熱を冷ましてあげる日常的な行為や、「猫舌」で苦労している大人たちの悩みを解決したいという思いがあります。
発案者であるユカイ工学取締役CMOの冨永翼氏は「自身の子育て経験から、早く、楽しく、かつ可愛く、適温の食事や飲み物を提供できればという思いから生まれた」と語ります。小型のファンで風を起こして熱いものを冷ます機能を持ち、マグカップやスープカップ、深めのお皿やお椀など様々な食器に対応しています。3分の使用で約-15℃の冷却効果があるといいます。
一方のみるみは、バッグに取り付け可能なチャーム型ロボットです。特に中国で大きな反響を呼び、海外のファッションブランドとのコラボレーションも決定しています。パリス・ヒルトンも興味を示したというこの製品について青木氏は「様々な方々に使っていただけたら」と期待を寄せています。
この2つの新製品は、クラウドファンディングで今年春から同時に展開予定とのことでした。
インタビューの終わり、「世界的なヒット商品を生み出していきたい」と意欲を語る青木氏。「ロボットとは『心を動かし、人を動機付けすることのできるインターフェース』」と定義し、彼らは人の行動をトリガーにして、まるで生き物と触れ合うようなやりとりを機械とできる世界の実現を目指しています。
日本の「可愛いロボット」が世界を埋め尽くす、そんな未来はもうそこまでやってきています。
関連リンク
関連記事
インタビューの記事
-

「AI レディ化に投資する」——変わり始めた日本企業
2026年02月19日
-

ワークフローが美しい国だから必ず勝てる——フライウィール横山直人氏が語る、AI 時代の日本企業の勝ち筋
2026年02月17日