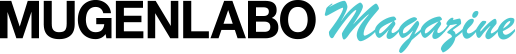- インタビュー
2021年01月14日
オープンイノベーションにおける「体験」の作り方ーービービット・藤井氏 Vol.2

- 株式会社ビービット
藤井 保文 - 東アジア営業責任者
前半のインタビューでは行動データに基づいた消費者の状況を細かく把握・仮説を立てることで新たなビジネス、製品のチャンスを伺う「バリュージャーニー」の考え方について伺いました。後半ではいよいよこの考え方を共創・オープンイノベーションにどう活用すべきかお話いただきます。複数のカルチャーが相乗りする企業同士の協業・共創でいかにしてひとつの体験、提供価値を生み出すことができるのでしょうか。(文中の質問者はMUGENLABO Magazine編集部、回答はビービット東アジア営業責任者、藤井保文さん。文中敬称略)
話を変えて。藤井さんは企業単位で新たな体験を生み出すロジックを説かれているわけですが、オープンイノベーションという文脈で、様々なカルチャーが混在する複数の企業が共同で一つの体験を生み出すことについて、どのような視点が必要だと思われますか
藤井:デジタル世界の理解を本当に全員が同じレベルで同じように見ている必要があるかというと、僕はそうではないかもなと思っています。例えば書籍にも記載した丸井さんの話が面白いです。丸井さんはデジタル社会に対応してはいるものの、必ずしもデジタルトランスフォーメーションを中心においていないんです。
昨今、デジタルネイティブなD2Cブランドがたくさん増えていますが、彼らは大きくなっていけばいくほど、ポップアップストアや実店舗を構えようとする傾向があるんです。このようなケースが生まれれば生まれるほど各社は同じような課題を抱えるようになる。
ではそこもターゲティングしておいて「リアル店舗プラットフォーム」というポジションを取りましょうとされてるのが丸井さんなんです。
デジタル化を旗振りして集まれ!とやるのではなく課題を先読みして待っている
藤井:いつかはデジタルネイティブ組がオフラインに進出したくなるだろう、という考え方は非常に戦略的なポジショニングだと思っています。
ですので、決して自社がデジタルに強くなっている訳ではないが「デジタル前提の世の中」に各社がどう対応するかを考えておき、かつ、そこと隣接するような状況を取りたいと考えているプレーヤーたちと手を組むのが一番シナジーが生まれるのではないかなと思っています。
自社アセットの強みを理解している企業には無理にパートナーを集めなくても集まってくる状況がありますが、もしかしたらそのあたりがポイントなのかもしれませんね
藤井:逆に言うと、この隣接する状況みたいなものを捉えずに「何か大きいからとりあえず組もう」みたいな形になってしまうと難しいですよね。事業化やコラボレーションの形を作るのが難しかったり、逆にユーザーに使われなかったり、みたいなことが発生する。
共創プロジェクトの旗振り役、担当者像ってどうあるべきですか
藤井:やはり軸の強さ、思いの強さは重要ですよね。とはいえ、大企業の中でイントレプレナーみたいに活動するのであれば、上司はやはり権限移譲しないといけないし、加えて部下も説明責任をちゃんと果たさないといけません。
例えば新規事業の話をしていて「上が理解してくれないですよね」みたいなのがあるんですけど、実際にどのような説明したのかを聞いてみると「いや、もうちょっと頑張ろうよ」みたいなケースが多いです。
どういうビジネスモデルになり得るとか、1年単位での収益性の話をしているのに、やろうとしていることは利益関係なく投資金を燃やして突き進むユニコーン企業が競合になるようなものだったりするとやはりおかしいですよね。また、やる上で企業全体のシナジーとして作っていくのかといった説明を追求せずに、何かこう「このままでは駄目だ」という話しかしないというのでは話は進みませんよね。
ただ、新規事業のロジックってあるようでなかなか難しい。結果的に打席に立った数勝負みたいなところもあります
藤井:それで言うと丸井さんが数年前に「信用の共創」というコア・バリューを作られたんですが、このプロセスがひとつ興味深いエピソードになるかもしれません。
『「信用の共創」とは、創業者の言葉「信用は私たちがお客さまに与えるものではなく、お客さまと共につくるもの」に由来するもので、丸井グループの創業の精神の一つです。創業時の商売は家具の月賦販売でした。当時高額だった家具を幅広いお客さまにご購入いただけるよう、当社が購入代金を一時お貸しして、それを月々の分割払いで返済していただくというものです。現金商売のように一期一会で売ったら縁が切れてしまうという関係ではなく、売った後も、10回、12回、24回払いなど、お客さまとお店とのお付き合いが長く続きます。
お支払いの遅れがなければ、ご利用可能金額が増え、ご利用期間が長くなるほどお客さまの信用はだんだんと上がっていきます。こうしたお客さまとのかかわりの中で、「信用はお客さまと共につくるもの」という精神が生まれてきました。このように私たちは、お客さまの年収や職業、資産の有無などに応じて一方的に信用を与えるのではなく、ご利用実績を通じてお客さまと双方向で信用を共に創っていく、つまり「信用の共創」を積み重ねてきたのです』
丸井グループ「玉ねぎの芯」より抜粋
丸井さんは一時期、経営が危なくなった時、創業当時まで系譜を辿ってその時からあった価値を見直されているんです。大手って過去の成功体験があるじゃないですか。それは明らかにその時代にマッチしたから成功した訳ですよね。
過去に答えがあるケースですね
藤井:でも、今の最新の環境変化から見るとその価値がなくなっているケースもある。書籍でスターバックスのケースをお伝えしてますが、あのようなリアルのサードプレイスはデリバリー前提の社会では成立しづらくなります。だからと言って本来の価値を見出さずに新しいことをやっても、もうそれは違う企業になっちゃうので意味がないですよね。
つまり、「その価値は何だったのか」という問い直しはすごく重要なんです。この不変の価値みたいなものを時代に合わせて再定義する、という行為は結果的に強い軸になり得るし、強いスタートアップの誰と組めばよいか、どのようなシナジーが生まれてくるのかが自然と見えてくることになると思うのです。

もう一点、中国企業との協業について意見をください。BATに代表される中国テック巨人の躍進や、米中摩擦における市場の分断、中国版NASDAQと言われる「STAR Market(科創板)」の開始など、中国との協業を検討する機会はさらに増えてくると予想されます。
藤井さんは著書「アフターデジタル(1・2)」で多くの中国企業について触れられていますが、協業・共創における文化的な違いなど含め、どのような視点が必要か教えていただけますか
藤井:確かに中国企業は貢献した人を潰すということをあまり考えない、ファミリー性を強く持っているのが特徴です。うちのファミリーに入るなら優遇します、コラボレーションのあり方も「トップと下の人たち」という経済圏内に限られるという傾向はありますね。大きくはAlibabaなのかTencentなのかのような陣営争いです。だから経済圏やどっち陣営なのかを把握しておくことはすごく重要です。
このあたりは日本の財閥系企業の繋がりとも通じるところですね
藤井:例えば中国市場で某飲料メーカーさんがAlibaba系列のモールに出店するとなったんです。期間限定ですよ。そこの提携発表会の会場に行ったんですが、Alibabaの方は「これは結婚です」って言うわけです。裏切ったらどうなるか分かってますか、の裏返しですよね(笑。中国企業とのお付き合いというのは婚姻関係に例えられるというのが実情です。
一歩踏み込んでますね
藤井:それと重要なのが早さで、日本企業が仮に中国企業とコラボレーションしようとすると、すごく上の方のレイヤーでの会話を「明後日までに」とサラッと言われたりする。そんなの絶対予定埋まってるじゃないですか(笑。
でも、当たり前のようにこれに対応できないと中国から切り離されてしまう。確かに大変ですけど逆に言えば、これに追い付きながら中国でテストマーケティングしていくようなことができると、単純な事業としてのコラボレーションだけでなく、企業としての世界レベルでの強さ、早さを手に入れることもできますよね。
新たな産業を生み出す力としての中国の現状をどのように見られていますか
藤井:中国が得意なのは限りなく「C」に近い「B」の部分です。
14億人いる中国なので、やはりC向けのビジネスが非常に強く、Alipayのような二面市場(消費者と事業者双方にサービス提供しているもの)を見ても、限りなくCに近いBの部分にアプローチしている点は、日本にはない知見が多く存在しています。
消費者向けの場合は行動データをベースに信用スコアを出して、どれぐらい貸し出せるかがわかるので金融とも繋がりやすい。そしてここには多くの事例があって特に新興国向けのビジネスとしてはこちらが得意です。
ビジネス向けの市場で注目している動向はありますか
藤井:感染症拡大でリモート前提になった時期、AlibabaやTencent、BytedanceからBusiness suiteが出て三つ巴で市場に浸透していったんです。SlackやZoom、Googleドライブ、Salesforceなどなど何でも入ってます。さらにコピー機の貸出みたいなこともセットでやってるケースもあって、かなり広範囲なワンストップ提供を始めてるんです。これがもっと多くの企業に導入され始めると、そこを基盤にまた新しい事業が生まれるかもしれないね、という話はしています。
逆に中国企業は日本をどう見ているのでしょうか
藤井:中国ではテクノロジーテンプレートみたいなのはどんどん出てくるんですが、一方でコンセプトを作るみたいな能力がやや薄い面はありますよね。ユニークネスみたいなところがあまり出てこないので、そこの意味では日本が重宝されています。例えば建物のコンセプトを作る場合、日本人の建築家は注目され続けています。
テクノロジーの分野ではドイツを一番メインに見てるって感じですね。工業的な意味合いだと車などは一日の長があるので、ドイツと比べても勝負できている。だから例えば車の中でどんな体験をするかっていうコラボレーションは可能性があるかもしれません。また、日本のことを長寿大国だと思っているので、領域的に高齢化社会に向けた医療や介護に関しては日本の知見が欲しいというのはありそうです。
長時間ありがとうございました。
関連記事
インタビューの記事
-

素材の力で未来を創る - マテリアルゲート
2026年02月03日
-

ニッポン発、今ここにない未来をつくる - POCKET RD
2026年01月29日