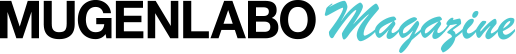- インタビュー
2021年01月14日
共創を成功に導く「バリュージャーニー」とはーービービット・藤井氏 Vol.1

- 株式会社ビービット
藤井 保文 - 東アジア営業責任者
日本の共創・オープンイノベーションに関わるキーマンの言葉を紡ぐシリーズ、今回はアフターデジタルの共同著者で、昨年7月にその第二弾となる「アフターデジタル2・UXと自由(日経BP)」を出版されたビービット東アジア営業責任者の藤井保文さんにお話を伺います。
人々の消費行動がより複雑になる現代、企業にはどのようなアプローチ・思考が求められるのでしょうか。藤井さんはこの点に対して消費者の動きを示す行動データに基づいた「バリュージャーニー」という思考フレームワークを提案されています。
東アジアを中心とする豊富な事例を元に、前編ではバリュージャーニーの考え方、後編では共創・オープンイノベーションにおける新しい体験の創出方法についてお話いただきました。(文中の質問者はMUGENLABO Magazine編集部、回答はビービット東アジア営業責任者、藤井保文さん。文中敬称略)
体験が重要視される時代の理由と「バリュージャーニー」
書籍にあるバリュージャーニーの考え方を改めてお聞きしたいのですが
藤井:アフターデジタルで語っていることを大きくビフォー・アフターで捉えた場合、これからの時代は特に「行動データが出てくる」点に大きな変化がある、という考え方を主眼にしています。モバイル・IoT・センシングといった技術革新のおかげで、これまでであればデータが残らなかった飲食や移動、支払いといった「行動」全部含めて履歴が残せるようになりました。これを前提とすると、できることが大きく変わってきます。
なるほど
藤井:人間ってある時はビジネスパーソンであったりある時は家庭人間であったりと、その時々の「モード」があると思うのですが、そのモードによって求めているものは違ってくるじゃないですか。一方、これまでのデータは属性などで人をざっくりとしか捉えられていなかったので、これだとモード毎の「最適なタイミング」にタッチできない。
これが行動データであれば最適なタイミングにタッチして正しいコンテンツを提供する、状況に合ったコミュニケーションをすることができるようになるんです。
行動データが加わることでタイミングが読めるようになると
藤井:今みたいにひとりの人の中にもたくさんの状況や視点があるという認識に立つことで、市場規模の新たな側面も見えてくるようになるはずです。また同時に顧客理解の解像度が高まることで、新しい製品企画につながる可能性も高まる。そう考えるとやはりこの行動データを活用できるかどうかが各企業にとって肝になってくる時代になっていると思いますね。
となると、どうやって行動データを取得するかがポイントです
藤井:ひたすらモノを売っているだけではやはり購買データしか得られません。これでは普段どういう行動をしているのか分からない。だから「製品販売型」から「体験提供型」にモデルを変える必要性が出てきます。
この「製品販売から体験提供へ」ということを、アフターデジタルでは「バリューチェーン型からバリュージャーニー型へ」という言葉で表しています。このバリュージャーニーにおける競争原理は「如何に良い体験を提供するのか」になります。
体験がひたすらよくないと消費者は使い続けてくれませんし、逆に使い続けてくれることによって、人々が「好きだ」と思ってくれているものに対して行動データが集まっていく構造になるわけです。だからちゃんと体験を作る、UXを作るってことが必要だよねと。
体験のよいサービスはリピートされるからそこでデータも得られて、というサイクルができる
藤井:これまでバリューチェーンとされていたものの多くは「製品を作って売る」ところにフォーカスしたビジネスプロセスでした。だからこのような体験提供型のビジネスモデルに対しては独自のビジネスプロセスを構築しないといけなかった。
製品は接点の一つでしかなく、それ以外のさまざまな体験などの接点を通して、顧客はその企業やサービスを判断するようになるのです。だから提供するものは製品ではなく「ジャーニー」になる。このジャーニーを作っていくビジネスプロセスが必要、という話なのです。

企業と消費者の間にある体験って、購入や利用、サポートなどかなり幅が広い印象です。こうなるとバリュージャーニーはかなり数が多くなるのではないでしょうか?
藤井:まず認識を整理したいのですが、バリュージャーニーを「作る」という作業とバリュージャーニーを運営後、「更新するという作業」があると考えています。バリュージャーニーを作る時はどのように接点を設計し、顧客と密な関係を作っていくのか、信頼関係を構築していくのかといった話です。
一方、実際そのユーザーが各接点を通して利用してくれて、その中から得られた行動データから「じゃあもっとこういう風なカスタマイズができる」とか「みんなはこの辺に困っているからこういう新しい機能を追加しよう」という運営の話があるんですね。この両方がセットになってバリュージャーニーが完成するんです。
体験を提供して行動データを取るまでのプロセスと、取った後の改善プロセスみたいな分け方ですね。ところで具体的にバリュージャーニーを「作る」上でのポイントはどういうものですか
藤井:UXをまとめあげる世界観やコンセプト、軸とは何かを考えることですね。
例えば、同じペイメントでも中国ではAlipayとWeChat Payの両方をみなさん使っています。なぜ同じようなサービスを両方使ってるのかと言うと、そのポジションが違うからなんです。Alipayは公共的なお支払いをするというイメージですし、本人たちのミッション・ビジョン・バリュー自体も「デジタル商取引を円滑にする」というところからきているので、とにかく商取引をスムーズにさせる存在なんです。
一方のWeChat Payは全てをコミュニケーション化する、例えば企業と個人であっても友達のようにコミュニケーションできるかどうかを一番上においてペイメント事業を展開しています。だから両者はインターフェースも全然違うし、機能の優先度も違うんです。本でも書いている話ですけど、ミッションによってUIまで全部変わっているケースです。
ここでいう具体的な体験のケースってどういうものですか
藤井:例えばお金を受け取る際、Alipayはお金を送ったら終わりです。受け取る作業はいらない。だから数人でご飯に行って割り勘しようとなっても、Alipayは送金したら終わりなんです。一方、WeChat Payは送金後に一つひとつ受け取るボタンを押す必要がある。
押し忘れたら回収できないし面倒に思うじゃないですか。でもね、違うんです。
ある日、レストランで上司が部下にご馳走するとします。そうするとお会計の際に、その部下がいやいや、私もお金出しますと財布を出す動作があるじゃないですか。上司が絶対払うとわかっているのに一応まず財布を出すみたいな。
それをWeChat Payはデジタル上でやらせてくれてるんです。つまり部下が上司に百元を送ってきてるんですけど、上司がその受け取りボタンを押さなければ払ったことにならないわけです。万が一受け取ろうとすると相手も、え?みたいな顔をしてくるんですよね(笑。
面白い。確かに体験が違いますね
藤井:これはあえて一手間増やすという、UI上で普通はやっちゃいけないようなことを組み入れることで、「お金の受け渡し」行為を「コミュニケーションの体験」とみなして余地を残そうとしているんです。逆にAlibabaからこれを見ると、どうしてわざわざ手数を増やして交渉取引をスムーズにしないんだ、となる。
ですから、みんなが何かを想起する状況に置かれた時、そのサービスとしての第一想起を取れるかどうかが重要になります。これが「状況ベースでのポジショニング」で、この定義がないまま、バリュージャーニーを作るのは本当に難しいものになってしまいます。(後半につづく)
関連記事
インタビューの記事
-

素材の力で未来を創る - マテリアルゲート
2026年02月03日
-

ニッポン発、今ここにない未来をつくる - POCKET RD
2026年01月29日