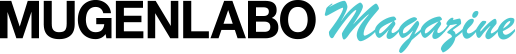- インタビュー
2025年07月16日
登壇32社紹介:KDDI ∞ Labo全体会登壇まとめ第3弾 ──XR・エンタメ領域等11社【2025年1月~6月・保存版】

全3回でお届けする、2025年上期KDDI ∞ Labo登壇スタートアップ紹介。第3弾では、XR・エンタメ領域等の11社をご紹介します。XR・エンタメ領域では、イマクリエイトの「するXR」が工業高校の溶接訓練で実用化され、mediVRの「mediVRカグラ」が脳卒中患者の歩行機能回復を実現するなど、「見る」から「する」への転換が医療・教育現場で具体的な成果を上げています。
その他領域では、ユアスタンドが EV 充電インフラの全国展開を加速し、脱炭素社会の基盤技術が実用段階に到達しています。また、TricoLogicは考える力を身につける学習塾「ミライ式」を展開するなど、AI 時代に対応した新しい教育手法という革新的なサービスを創出しました。
XR・エンタメ領域
「見る」から「する」へ──XR・エンタメ領域は、体験の質的転換を遂げています。イマクリエイトの「するXR」が工業高校や企業の溶接訓練に導入され、mediVRの「mediVRカグラ」が脳卒中患者の歩行回復を実現。従来のエンターテインメント用途を超え、産業や医療の現場で「不可能を可能にする」技術として定着しつつあります。
さらにバーチャル空間での身体性を伴う体験の実現も進んでいます。DataMeshの「FactVerse」は Gartner社の新興技術影響力レーダーレポートに入選し、ユビタスはクラウドゲーミングの先駆者として観光産業向け LLM開発まで手がけています。
一方、cizucuのコミュニティ・ストックフォトやATOMicaの全国53施設でのソーシャルコワーキングなど、デジタル技術を活用した新しいコミュニティ形成も注目されています。
これらの企業が描く未来は、物理とデジタルの境界が溶け合い、誰もが創造的な体験を享受できる社会です。
XR・エンタメ領域6社紹介
- バーチャル空間内で身体性を伴う体験を可能にする – イマクリエイト
- クラウドゲームソリューションを提供 – ユビタス
- ゼロコードで3D+XRフローデザイン&トレーニングプラットフォームを提供 – DataMesh
- 最新テクノロジーを用いて革新的な医療ソリューションを提供 – mediVR
- コミュニティ・ストックフォトアプリ – cizucu
- 共創を持続的に生み出すソーシャルコワーキング – ATOMica
- 移動をもっとクリーンに!EV 充電を提供 – ユアスタンド
- 「移動」を価値にするモビリティデータプラットフォーム – Essen
- 世界最大の荷物預かりネットワーク – Bounce
- 東大発!AI 時代に必要な考える力を伸ばす学習塾 – TricoLogic
- 日本で唯一の実用化!無人決済サービスソリューション – TOUCH TO GO
- 登壇32社から見えてきた技術トレンドとは?──KDDI ∞ Labo全体会登壇まとめ第1弾・AI領域12社【2025年1月~6月・保存版】
- 登壇32社紹介:KDDI ∞ Labo全体会登壇まとめ第2弾 ──DeepTech、サステナビリティ領域9社【2025年1月~6月・保存版】
- 今登壇25社から見えてきた課題傾向とは?ーーKDDI ∞ Labo全体会登壇まとめ第1弾【1月~6月・保存版】
- 登壇25社領域別紹介:KDDI ∞ Labo全体会登壇まとめ第2弾ーーAI、XR、SaaS、フィンクテック領域スタートアップ【1月~6月・保存版】
- 登壇25社紹介:KDDI ∞ Labo全体会登壇まとめ第3弾ーーモビリティ・エンタメ・ヘルスケア・環境領域スタートアップ【1月~6月・保存版】
-

素材の力で未来を創る - マテリアルゲート
2026年02月03日
-

ニッポン発、今ここにない未来をつくる - POCKET RD
2026年01月29日
-

MUGENLABO UNIVERSEから生まれた新たな教育の形 ― ライフイズテックとアストロスケールが描く「宇宙×デジタル」の未来
2026年02月10日
-

素材の力で未来を創る - マテリアルゲート
2026年02月03日
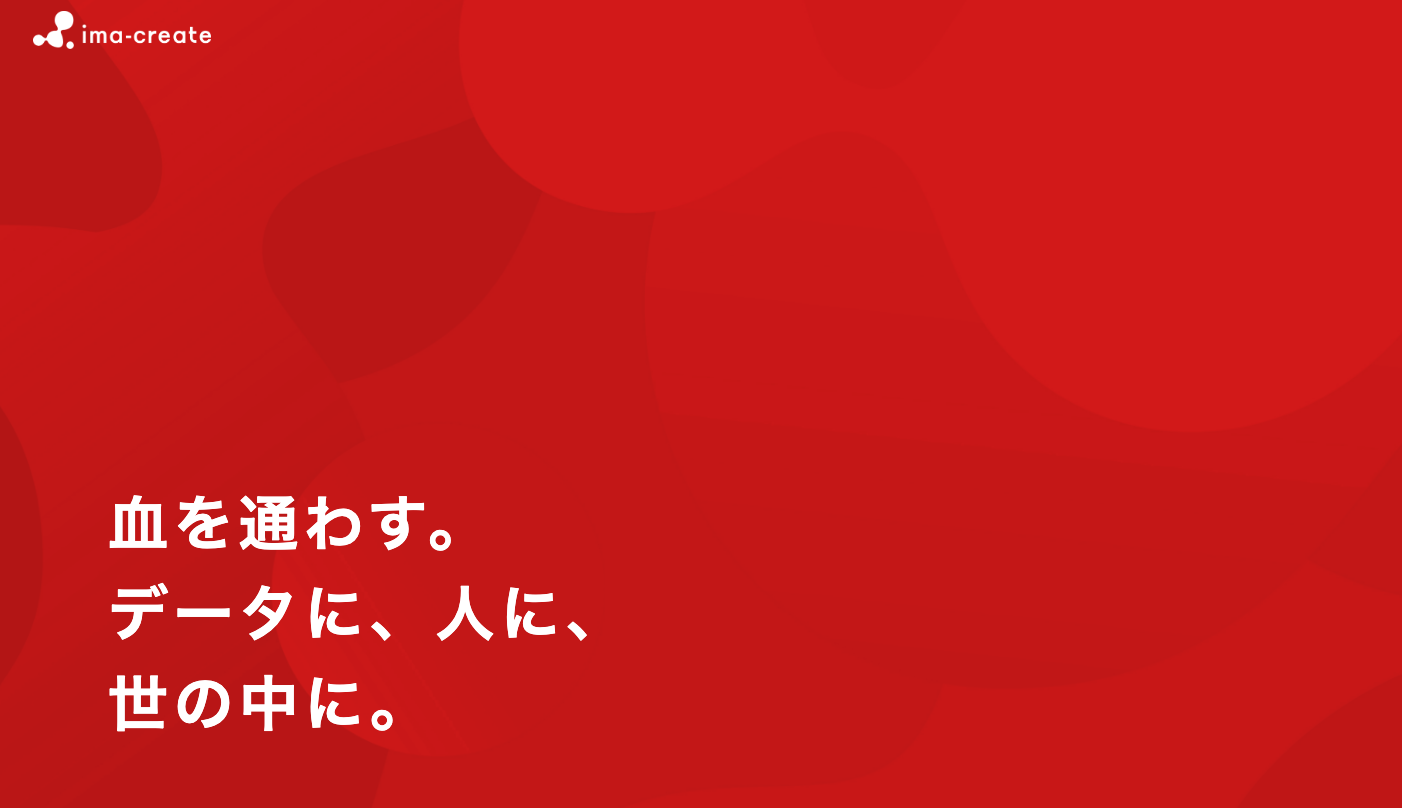
イマクリエイトは、バーチャル空間内での身体性を伴う体験を可能にする XR技術「するXR」を開発しています。事業開発責任者の重田雄基氏は、CEOの山本氏が住友商事在職中にトルコでクーデター未遂という希少な体験をしたことをきっかけに、やりたいことはすぐ行動に起こさなければと思い、起業を決意したと語っています。
同社はコベルコE&M社と推進している「ナップ溶接トレーニング」を工業高校や民間企業の新人教育として国内外で導入。仮想空間でのトレーニングやシミュレーションのコンテンツ開発・販売を行い、課題を有する大企業との協業により開発・販売を進めています。
今後は、仮想空間で違和感なく「するXR」を生かして、生産・製造準備や技能承継の課題を解決していく予定です。製造業のDX化により、モデルベース開発や設計のフロントローディング化が進んでいる中、人の関わる工程は「モノを流して試しに作業してみないと分からない」という現場の課題を解決することを目指しています。

ユビタスは、クラウドテクノロジー企業として大手ゲーム会社にクラウドゲームソリューションを提供しています。シニア・ディレクターの中坪知幸氏は、すべてのベンチャー企業には「イノベーション」の血が流れており、ユビタスも例外ではないと語っています。
同社は生成AIソリューションの提供やLLM開発も手がけ、AIバーチャルヒューマンのUbiOne、画像生成AIツールのUbiArtなどを展開。観光産業向けの405LLM/基盤モデル開発も進めています。非ゲーム領域でも、メタバースなどのリッチコンテンツ配信のストリーミング配信を可能にするクラウドソリューションを提供しています。
同社のクラウド技術により、リッチコンテンツのストリーム配信が可能となり、ゲームやメタバースなどのコンテンツは年々リッチ化していますが、ブラウザが起動するデバイスであれば性能を問わず顧客に届けることができます。多くの社会課題の解決を生成AIアプリケーションで実現することを目指しています。
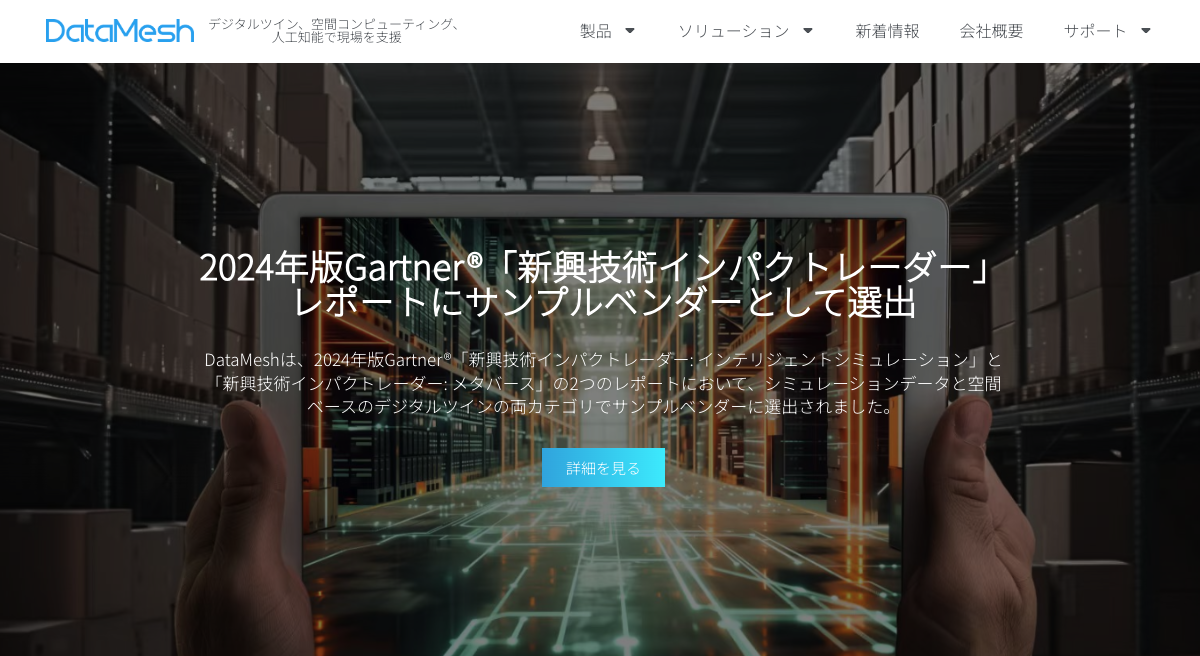
DataMeshは、産業用メタバースプラットフォーム「DataMesh FactVerse」を提供しています。代表取締役の黄宇氏は、XR/デジタルツイン技術を活用したアプリケーションの企画・開発・提供及びシステム開発支援を行っています。
同社は産業メタバースプラットフォームの研究開発に注力し、デジタルツイン、XR(拡張現実)、人工知能、IoTなどの技術を用い、デジタルツインソリューションを提供し、産業企業のデジタル変革を支援しています。デジタル世界と現実世界をつなげ、デジタルツイン、空間コンピューティング、AI(人工知能)で現場技術者を支援することを目指しています。
「DataMesh Director」は、ゼロコードで3D+XRフローデザイン&トレーニングプラットフォームを年間96万円から提供。Gartner社の新興技術影響力レーダーレポートにも入選し、世界最先端のXR/デジタルツインソリューションを提供しています。

mediVRは、仮想現実(VR)技術を活用した「体性認知協調療法」により、脳卒中や神経疾患などの難治疾患を克服するための医療機器「mediVRカグラ」を開発しています。代表取締役社長の原正彦氏は、循環器内科医として働く中で、現在の医学では治療困難な疾患に対するVR技術を用いた治療アプローチを思いつき、2016年に大阪大学発ベンチャーとして創業しました。
同社のVRリハビリテーション医療機器は、仮想空間上でのリーチング動作を繰り返すことで姿勢バランスや認知処理機能を鍛える「脳再プログラミング療法」とも呼ばれています。VR空間で特定の運動課題に取り組むことで、神経回路を再構築可能であり、対象疾患によらず高い治療効果を発揮します。
「mediVRカグラ」は、リハビリテーション領域における新たな標準を創出するデジタル医療機器です。世界で初めて、既存治療を超える成果を出しているデジタル治療として、日本での保険収載を取得し、国民が等しく治療を享受できる世の中を目指しています。

cizucuは、写真を撮影するクリエイターが自由に表現できる場を提供し、企業が販促や広報で必要な写真素材を簡単に獲得できるコミュニティ型のストックフォトサービスを提供しています。代表取締役CEO兼CTOの太田優成氏は、2度と戻ってくることのない20代という貴重な時間を、最高の仲間とともに最高のサービスを作りたいと考えたことから起業しました。
同社は画像解析技術と多言語対応を活用し、クリエイターの作品をグローバルに発信する仕組みを備えています。独自の強みとして、画像解析技術と多言語対応により、クリエイターには作品の露出機会と収益化の可能性を、企業には販促や広報活動のための高品質な写真素材を提供しています。
今後はフォトコンテストや写真管理、アプリ内広告などの複数の収益モデルを確立させ、クリエイターの表現活動と企業のマーケティング活動を支援するビジネスモデルを構築していきます。アナログな動作と生成AIをはじめとする最先端のデジタル技術を融合させ、誰もが自由に写真で表現できる社会を目指しています。

ATOMicaは、多種多様な場とコミュニティの企画・運営を通じて共創を持続的に生み出すソーシャルコワーキング事業を展開しています。代表取締役Co-CEOの嶋田瑞生氏は、小学生・中学生の頃、学校に行くのが辛い中で友人に支えられ楽しい学校生活を取り戻せた体験から、多種多様な人々に「頼り頼られる関係性を増やす」ことがウェルビーイングに直結すると考えています。
事業の核の1つであるコミュニティマネージャーの在籍数は2025年6月現在232名(正社員、業務委託、アルバイト合計)となり、その活躍の場は従来の地域共創施設やスタートアップ施設に加え、大学内共創空間や企業内施設へと広がっています。ATOMica が運営する全国29都道府県・53施設に常駐しながら、企画・運営、コミュニティづくりを担っています。
自社開発 SaaS「knotPLACE(ノットプレイス)」の導入先施設数は120を超え、全国の人・企業・地域を結ぶキャリアプログラム「Coyage(コヤージュ)」、国内最大級のカスタマーサクセスコミュニティを抱えるCS特化型BPO事業「KOMMONS(コモンズ)」なども展開しています。
その他領域
脱炭素社会への移行が加速する中、ユアスタンドは国内5,000基のEV充電インフラを構築しています。
また、Bounceは世界100か国・20,000拠点の荷物預かりネットワークを展開し、Essenが人流データを活用した広告プラットフォーム「WithDrive」を展開するなど、移動そのものを新たな価値創造の源泉として捉える発想も生まれています。
さらに、AI時代に対応した新しい教育手法と人手不足を解決する革新的なサービスが登場しています。
その他領域5社紹介

ユアスタンドは、電気自動車(EV)向けの充電スタンドの設置工事から、充電予約・課金のためのソリューション提供まで、ワンストップで提供しています。専務取締役CFOの進藤亮佑氏は、創業者の浦が環境問題への貢献活動の一環として自身でEVを購入したところ、自宅(集合住宅)でのEV充電の導入がとても不便であることに課題感を持ったことから起業したと説明しています。
国内の累計設置実績は概ね5,000基で、とりわけ分譲マンションでの設置基数ではトップクラス。自宅・職場といった「基礎充電」領域に軸足を置いて事業を進めており、自宅・職場にEV充電環境があることにより、充電のためにわざわざ遠くの充電スタンドに出向いて高額な充電料金を支払う必要がなくなります。
EVは脱炭素の観点からも自動運転の観点からも、2030年代のモビリティ社会には欠くべからざるツールです。日本では、まだまだガソリンスタンド型のエネルギー補給の考え方が根強いですが、近い将来、スマートフォンの充電と同じく、EVも自宅や職場で充電することが当たり前の社会となることを目指しています。
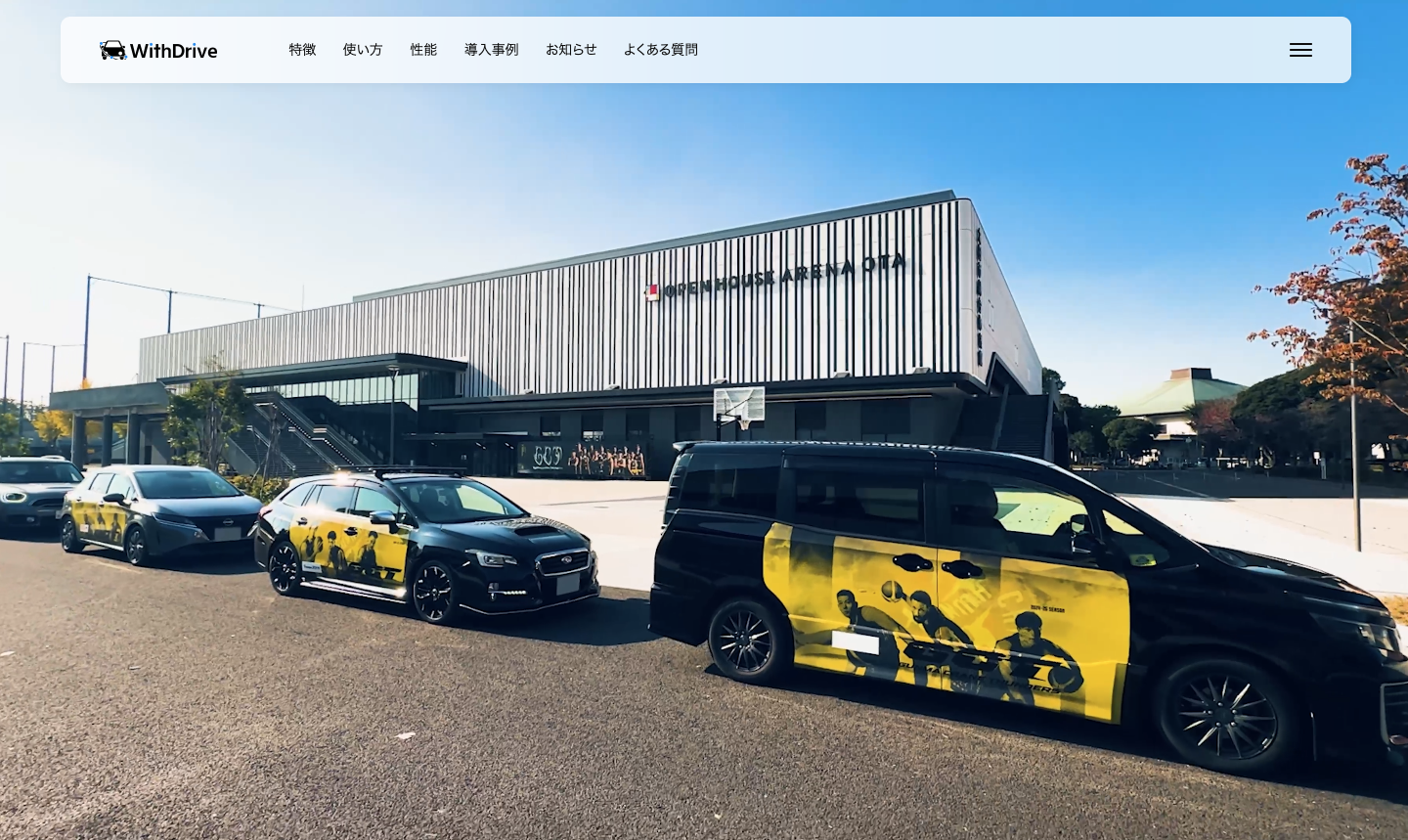
Essenは、モビリティ広告プラットフォーム「WithDrive」を展開しています。代表取締役の橘健吾氏は、大学院入試の勉強をしていた当時、車にコタツと布団を積んで日本中を移動しながら勉強していた時期があり、とある地方で"自転車のロゴが入った自転車"を目にした瞬間、「移動には広告価値がある」と直感したことが起業の原点となりました。
同社のサービスは、車両に取り付けたラッピング広告やLEDサイネージを活用し、人流データを基に広告効果を可視化する技術を開発。最大の特長は、車両が走行することで収集される人流データや視認データをもとに、広告の効果を可視化し、エリアや時間帯ごとにターゲティングの最適化ができる点です。
従来の屋外広告では困難だった広告の成果測定と柔軟なPDCAを可能にし、自治体や地域企業、大手ブランドなど多様なクライアントのニーズに対応。取得した行動データをもとに、広告領域にとどまらず、スマートシティ、防災、観光誘導、さらにはライフスタイル提案といった分野への応用も進める予定です。

Bounceは、世界中の地域ビジネスと提携し、旅行者や地元の方々のために余ったスペースを手荷物預かり所として活用するマーケットプレイス型のサービスです。CEOのCody Candee氏が新しい街に到着したとき、荷物を預けて身軽になり、安心して観光を始めたいという瞬間に、荷物に縛られることなく、もっと自由に世界を探索できるようなサービスをつくりたいという想いから起業しました。
100か国以上にわたって20,000以上の拠点を展開する世界最大の手荷物預かりネットワークを運営。観光中でも、フライトの前でも、街中を移動する途中でも、Bounceがあれば荷物を安全に預けられ、どこでも手ぶらで自由に過ごすことができます。同社のサービスは、荷物補償、24時間365日のサポート、App Storeで4.9の高評価を誇り、世界中で多くのユーザーに選ばれています。
2026年末までに世界30,000拠点のネットワーク構築を目標に掲げており、このインフラが整えば人々が新しい場所に到着した瞬間から荷物を預けたり、必要な物を受け取ったり、旅のスタートに必要なすべてをすぐに整えることができる世界が実現します。

TricoLogicは、「キャラフルな世界」というビジョンのもと、AI時代に必要な考える力を身につける学習塾「ミライ式」を展開しています。代表取締役CEOの西尾彰将氏は、東大松尾研初のスタートアップとして、一人ひとりが個性を発揮し活躍できる社会を目指しています。
ミライ式は、全科目の全範囲を先取り学習することで子どもたちの成績を上げつつ、すべての科目で「自分の意見」を書く練習を行います。この意見データから、子どもたちの好き嫌いや得意不得意を抽出し、おすすめの「読書・教材・習い事・職業」などを幅広くレコメンド。地域の連携施設への送客も行い、子どもたちが図書館に行くきっかけを作るなど、地域資本を活用するインフラとしても機能しています。

TOUCH TO GOは、「日本で唯一実用化されている省人化・無人決済店舗システム」を提供するスタートアップです。代表取締役社長の阿久津智紀氏は、生産年齢人口が30%不足する2050年に向けて、いつでもどこでも便利に買い物できる世界を作ることを目指しています。
同社のサービスは、実店舗から極小店舗・サテライト・職域売店・ポップアップストア向けに展開し、「未来を実現する」サービスを生み出しています。大企業のアセットを活かしたカーブアウトスタートアップの事例として、リテール、人手不足、人や物を補足する技術を活用したサービスを提案しています。
まとめ
XR・エンタメ領域等の11社をご紹介しました。これらの企業に共通するのは、従来の概念を覆す技術革新により、新しい体験や価値の創出を実現していることです。
XR 技術は単なる「見る」体験から「する」体験へと進化し、医療や教育の現場で具体的な成果を上げています。その他の領域では、移動そのものを新たな価値創造の源泉として捉える発想やAI時代に対応した新しい教育手法と、人手不足という社会課題を解決する、様々な革新的サービスが生まれています。
2025年下期も、KDDI∞Laboからの新たな革新企業登場にご期待ください!