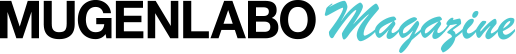- インタビュー
2025年07月15日
登壇32社紹介:KDDI ∞ Labo全体会登壇まとめ第2弾 ──DeepTech、サステナビリティ領域9社【2025年1月~6月・保存版】
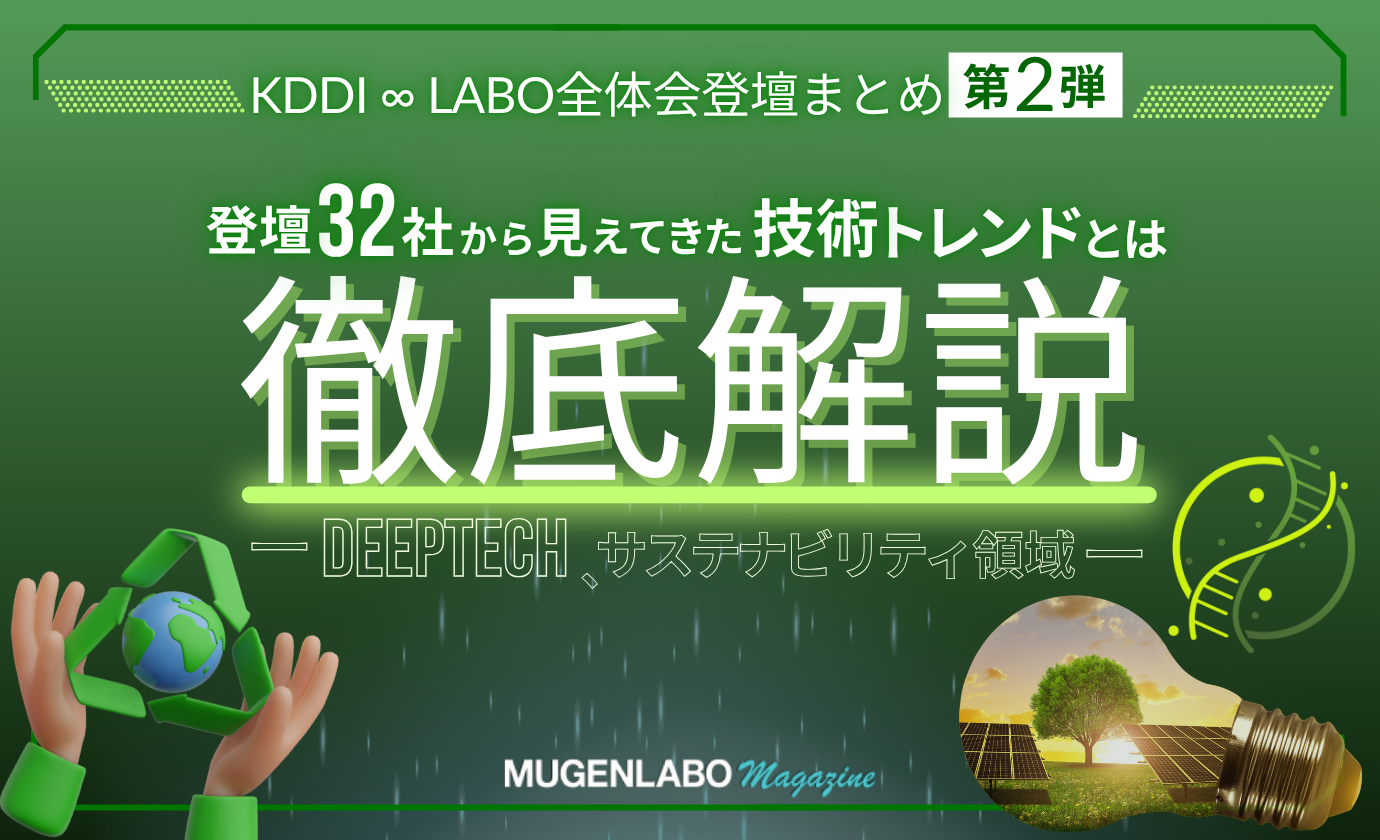
全3回でお届けする、2025年上期KDDI ∞ Labo登壇スタートアップ紹介。第2弾では、DeepTech、サステナビリティ領域の9社をご紹介します。これらの企業は、日本の強みである製造業の高度化、次世代エネルギー技術、循環型社会の実現を担う存在として注目を集めています。
DeepTech領域
日本の産業競争力の源泉となる製造・材料・バイオテックなどのDeepTech領域では、AI 技術による製造プロセス最適化、伝統素材の再定義、次世代エネルギーの実用化、医療技術の革新など、深い専門性を活かした技術開発が進んでいます。
例えば、アイクリスタルのプロセスインフォマティクス(PI)による製造効率化や、ユナイテッドシルクの「シルクを未来の産業に変える」取り組み、MiRESSO の核融合発電に不可欠なベリリウム精製技術など、大学発スタートアップが持つ研究開発力が商業化段階に到達しています。
この他、AOI Biosciences のネオセルフ理論に基づく検査創薬事業や、Butlr Technologies の MIT 発 AIoT 人間センシングプラットフォームなど、基礎研究から実用化まで一貫した技術開発により、グローバル市場での競争力を確立しつつあります。これらの企業が描く未来は、日本の技術力と創造性が世界の産業変革を牽引する社会です。
DeepTech領域5社紹介
- AI 活用で製造プロセスの最適化を目指す – アイクリスタル
- シルクの力で、新しい未来を実現 – ユナイテッドシルク
- ベリリウム(Be)でフュージョンエネルギーの社会実装を目指す – MiRESSO
- ネオセルフ理論に基づく検査創薬事業を展開 – AOI Biosciences
- 熱センサーによる、AIoT プラットフォームを開発 – Butlr Technologies

アイクリスタルは、「モノづくりのプロセスを最適化し、持続可能で豊かな世界の創造」を目指す名古屋大学発のスタートアップです。代表取締役の髙石将輝氏は、プロセスインフォマティクス(PI)を活用した製造業の製造プロセス最適化を手がけています。
同社は独自のプロセスインフォマティクス手法を用い、製造業の製品開発や製造プロセスにおける試行錯誤の時間を圧倒的に短縮。「製造コンサルティング、受託解析、顧問、教育など、お客様の各フェーズに応じたワンストップサービスを提供しています」(髙石氏)。今後は装置ごとの個別最適化から、複数のプロセスを一気通貫で最適化する「メタファクトリー」の構築を目指しています。

ユナイテッドシルクは、「伝統素材であるシルクを、未来の産業に変える」という強い想いのもと、シルクのトータルソリューションカンパニーとして活動しています。執行役員の清谷啓仁氏は、従来は繊維用途に限定されてきたシルクを、化粧品原料、食品素材、医療用途、さらにはバイオ素材へと再構築していると説明しています。
同社は独自の精製・分離技術を活用してシルクの主要構成成分であるフィブロインを高純度で抽出し、原料の生産から用途開発、パートナーとの製品化支援までを一貫して担っています。化粧品では高機能かつエシカルなシルク由来成分の提供、食品では健康食品や機能性食品への応用、さらには生分解性容器の開発など、多岐にわたる分野で展開しています。

MiRESSOは、次世代エネルギーである核融合発電の社会実装に向けて、その鍵となるベリリウム(Be)の安定供給体制を構築するスタートアップです。上席エンジニアの浜崎浩氏は、「我が国の資源セキュリティに貢献し、次世代のカーボンニュートラルなエネルギー源であるフュージョンエネルギーをベリリウムの力で支える」と語っています。
同社は青森県において低温精製技術を用いたパイロットプラント「BETA(Beryllium Testing Plant in Aomori)」を整備中で、2027年度からのベリリウム製造・販売の本格開始を目指しています。量子科学技術研究開発機構(QST)で開発された低温精製技術により、従来手法よりも低コスト・省エネルギーで純度の高いベリリウムの精製を実現しています。
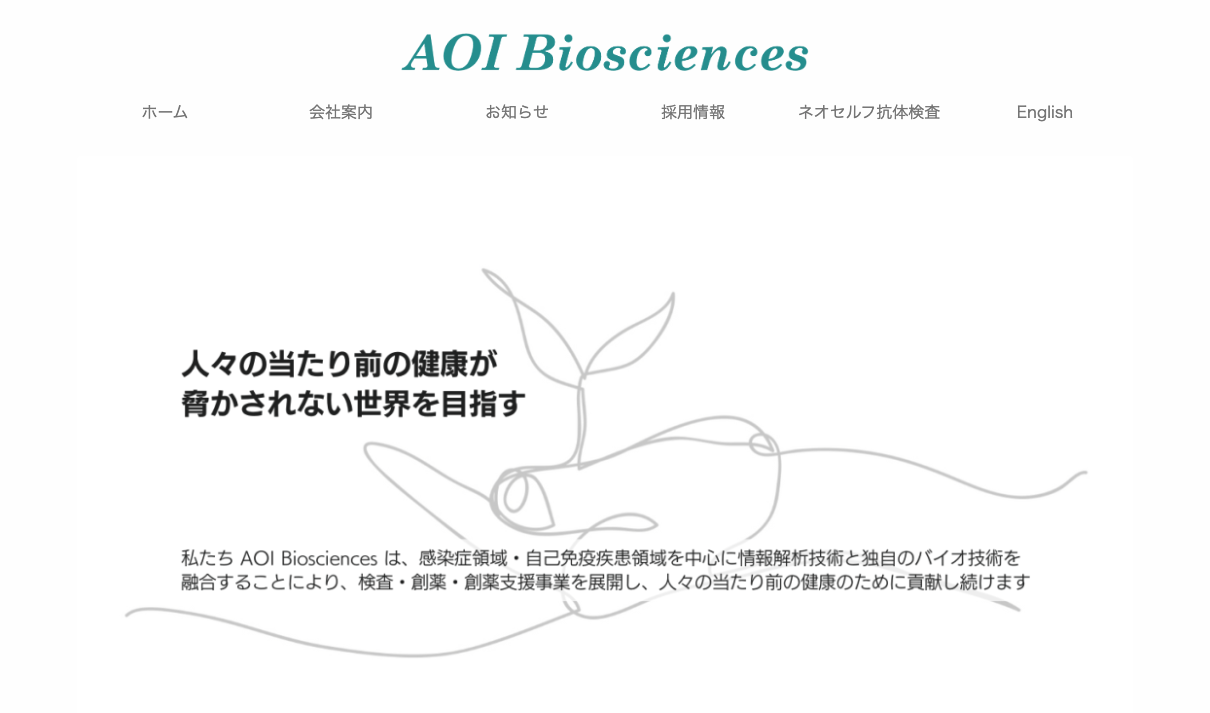
AOI Biosciencesは、「人々の当たり前の健康が脅かされない世界を目指す」ことを使命に、感染症領域・自己免疫疾患領域を中心に情報解析技術と独自のバイオ技術を融合したサービスを展開しています。代表取締役社長の末田伸一氏は、大学卒業後に腎臓内科医として6年間臨床に従事した経験を活かし、「当たり前の健康」を守りたいという想いから起業しました。
同社は自己免疫疾患の新規メカニズムであるネオセルフ理論に基づく検査創薬事業と、生体情報解析技術に基づく創薬・創薬支援事業を展開。特に不妊症・不育症の検査である「β2GPI ネオセルフ抗体検査事業」に注力し、全国200以上の医療機関に導入されています。

Butlr Technologiesは、「プライバシーを守りながら、よりスマートで効率的な空間を創る」ことを使命とする MIT 研究室発のテック企業です。APAC Regional Manager の Rang Luo氏は、建物内の利用率、混雑状況を正確かつ匿名で推測するために熱信号を使用する AIoT 人間センシングプラットフォームを開発していると説明しています。
同社のサービスは、GPS が不得意とする屋内測位や垂直方向測位を可能にし、オフィスのレイアウト最適化、スマート清掃、AI によるライト・空調コントロールなどの建物運営をサポート。Boeing、Verizon、Meta、Netflix、Walmart、KDDI、阪急阪神不動産などの世界最大級企業から信頼を得ています。
サステナビリティ・エネルギー領域
「ごみ」という概念そのものをなくすサステナビリティ・環境技術領域は、従来の環境対策を超えた根本的な社会変革に挑戦しています。レコテックの「pool」は廃棄物情報を可視化し、資源循環のマーケットプレイスを創出。プラ新法の大臣認定を取得し、関東圏から九州、関西へと全国展開を進めています。
一方、JOYCLE の「JOYCLE BOX」は「運ばず、燃やさず、資源化」をコンセプトに、病院や離島などの高コスト処理地域をターゲットとした分散型アップサイクルプラントを展開。2027年にはフィリピン、インドネシアの海外リゾート地への進出も計画し、グローバルな環境課題解決を目指しています。
両社に共通するのは、廃棄物を「問題」ではなく「資源」として捉える発想の転換です。IoT 技術とプラットフォーム化により、従来の「処理」から「循環」へと産業構造の根本的な変革を推進。「資源と喜びが循環する社会」の実現に向けて、日本発の技術とビジネスモデルが世界の環境問題解決に貢献することが期待されています。
このほか、未利用エネルギーの活用も進んでいます。elleThermo の「半導体増感型熱利用電池(STC)」は、データセンターの排熱から家庭の体温まで、あらゆる熱源を電力に変換可能。アスソラは農地と太陽光発電を両立させる「ソーラーシェアリング」で、土地利用の新しいモデルを提示しています。
サステナビリティ・エネルギー領域4社紹介
- 廃棄物の情報を可視化し社会の資源循環を促進 – レコテック
- 分散型アップサイクルプラント提供 – JOYCLE
- 再生可能エネルギーで、持続可能な地球を目指す – アスソラ
- 未利用排熱のエネルギー変換 – elleThermo

レコテックは、「世代間責任を果たす」をミッションに掲げる Climate Tech カンパニーです。執行役員の荒井亮介氏は、社会の資源循環を促進させるプラットフォーム「Circularity Design Tool - pool」を展開していると説明しています。
pool は、廃棄物の発生情報(量、場所、時期、種類など)を可視化し、廃棄物を再生資源として循環させるマーケットプレイスをつくるプラットフォームです。百貨店や商業施設、オフィスビル、マンション、工場など様々な廃棄物発生現場へ導入し、プラスチック、生ごみ、廃食油などあらゆる資源を循環させています。同社は、pool が道路や水道、電気のように、循環型社会に必要不可欠なインフラとなることを目指しています。

JOYCLEは、「資源と喜びが循環する社会を創造する」をミッションに掲げ、ごみを「運ばず、燃やさず、資源化」する IoT アップサイクルプラント「JOYCLE BOX」を開発しています。代表取締役社長の小柳裕太郎氏は、「死後100年の社会を変える」ビジネスを創りたいという想いから起業しました。
JOYCLE BOX は、人口減少の中で発生するごみ焼却炉寿命問題・ドライバー不足問題・産業廃棄物処理コスト上昇問題を解決します。特に処理コストの高い病院や焼却炉から遠い離島・地方をターゲットとし、2027年からはフィリピンやインドネシアの海外リゾート地への進出も計画しています。

アスソラは、再生可能エネルギー発電事業の開発とコーポレート PPA による電力供給を手がけています。代表取締役の山崎智広氏は、幼い頃から環境問題に強い関心を持っており、太陽光や風力といった自然エネルギーがいまだ十分に活用されていない課題を、経済活動と連動したアプローチで解決することを目指しています。
脱炭素化に取り組む企業との間で、コーポレート PPA という再生可能エネルギーの電力を供給する契約を締結し、クリーンな電気を供給。第1号案件として東北電力との長期コーポレート PPA に基づき、2025年より再エネ電力の供給を開始。農地上部に太陽光発電設備を設置する営農型太陽光(ソーラーシェアリング)にも積極的に取り組んでいます。
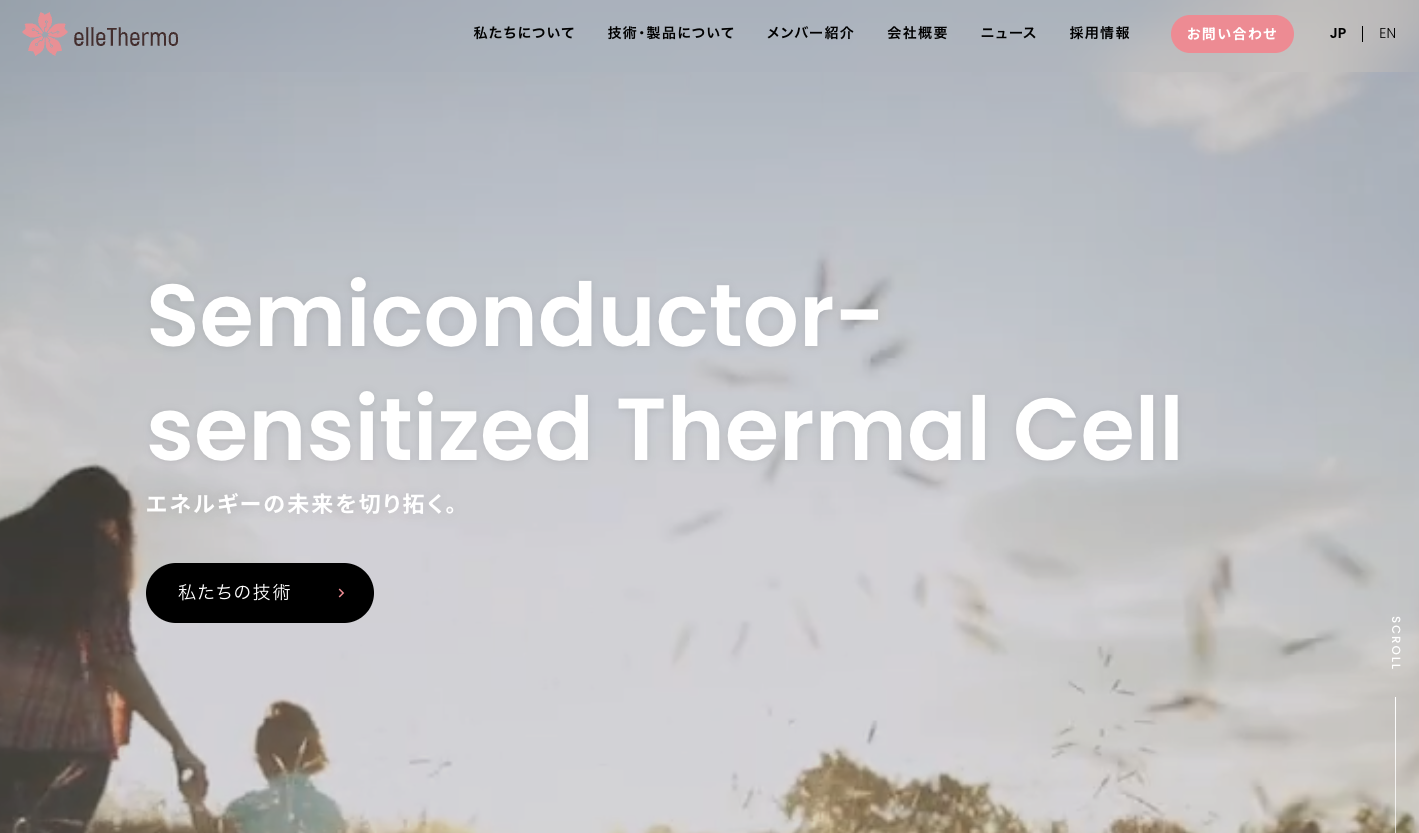
elleThermoは、未利用排熱を電力へ変換する新しいエネルギー変換技術「半導体増感型熱利用電池(STC)」の普及を通じて、エネルギー問題の解決を目指しています。代表取締役 CEO & Founder の生方祥子氏は、2011年の大地震時に電力の重要性を再確認し、娘の未来を託せる安全・安心な理想の発電技術を考え抜いた結果、2015年に熱エネルギー変換技術の着想を得ました。
STC は、半導体の中で生まれた熱励起電荷が電解質イオンを酸化・還元して発電する技術です。室温を含む0℃以上の温度帯で発電でき、薄く軽いシート状の基本構造により、設置場所や設置スペースに柔軟に対応可能。AI やクラウドサービスの普及に伴い半導体工場やデータセンターの増加・大規模化が進む中、データセンターから工場、発電所、身の回りの未利用排熱まで幅広く活用できます。
まとめ
製造・材料・バイオテック等のDeepTech領域では、AI 技術による製造プロセス最適化、伝統素材の新たな活用方法、次世代エネルギーの実用化、医療技術の革新など、日本の強みを活かした技術開発が進んでいます。特に、大学発スタートアップが持つ深い専門性と、グローバル市場を見据えた事業展開の組み合わせが印象的でした。
サステナビリティ・環境技術領域では、単なる環境負荷低減にとどまらず、廃棄物を資源として活用する循環型社会の実現に向けた具体的なソリューションが登場しています。特に、IoT 技術とプラットフォーム化により、従来の廃棄物処理の枠組みを超えた新しいビジネスモデルが創出されています。
次回第3弾では、XR・エンタメ領域の企業をご紹介しますのでお楽しみに!
関連リンク
関連記事
-

素材の力で未来を創る - マテリアルゲート
2026年02月03日
-

ニッポン発、今ここにない未来をつくる - POCKET RD
2026年01月29日
インタビューの記事
-

MUGENLABO UNIVERSEから生まれた新たな教育の形 ― ライフイズテックとアストロスケールが描く「宇宙×デジタル」の未来
2026年02月10日
-

素材の力で未来を創る - マテリアルゲート
2026年02月03日