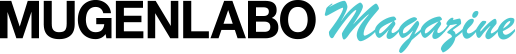- インタビュー
2025年07月14日
登壇32社から見えてきた技術トレンドとは?──KDDI ∞ Labo全体会登壇まとめ第1弾・AI領域12社【2025年1月~6月・保存版】
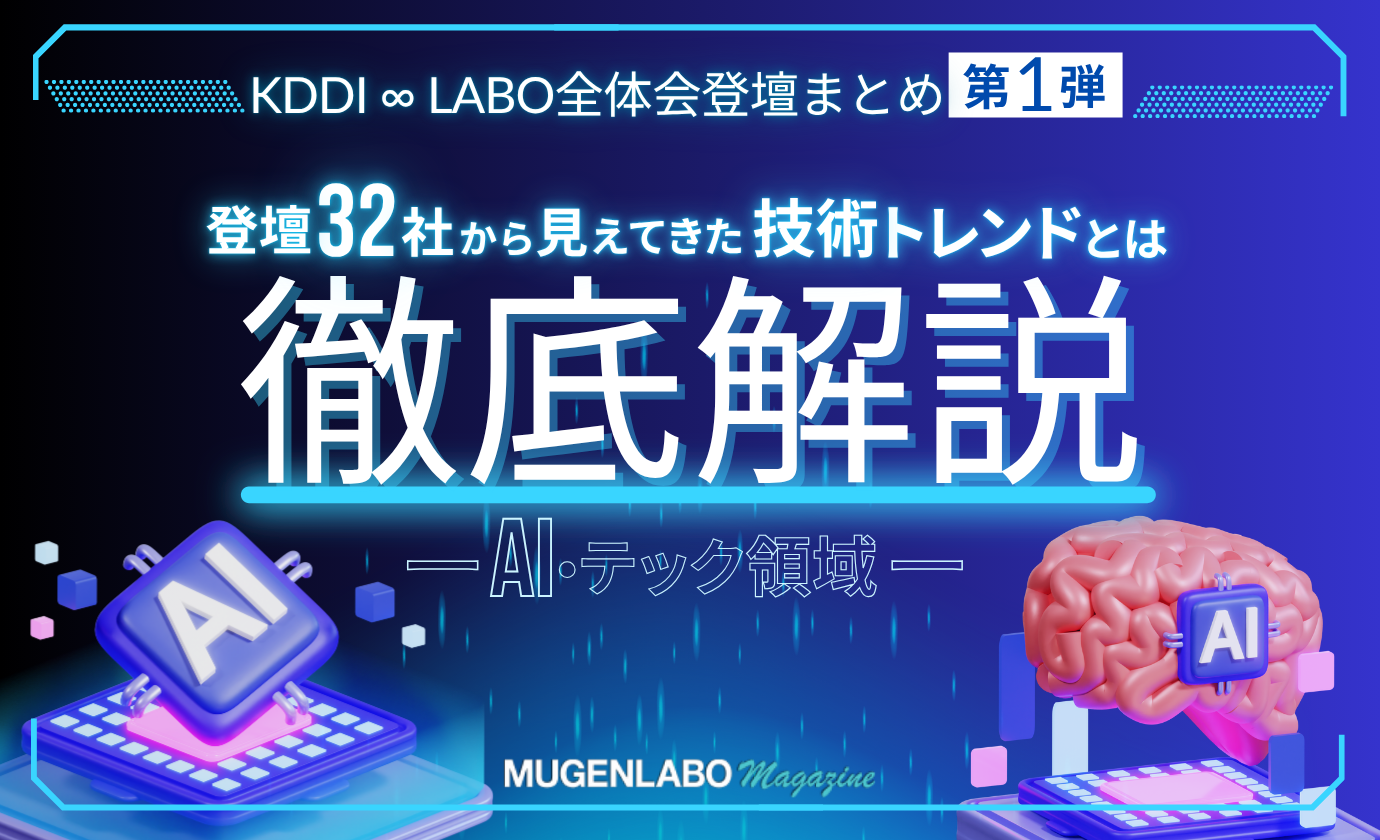
KDDI ∞ Laboで定期開催している月次全体会。今回は、2025年1月から6月までにご登壇いただいたスタートアップ32社をまとめてご紹介いたします。2024年下期から継続して、AI・生成 AI 分野の実用化が加速する一方で、XR 技術の産業応用や脱炭素技術の多様化など、テクノロジーの社会実装がより具体化した半年間となりました。
領域別全体傾向
登壇いただいたスタートアップ32社を領域・技術別にみてみると、「AI関連」が最も多く12社、続いて「XR・エンタメ関連」が6社、「モビリティ・エネルギー・インフラ」が5社、「製造・材料・バイオテック」が5社、「サステナビリティ・環境技術」が2社、「EdTech・サービス」が2社となっています。
特に注目すべきは、AI・テック系企業の中でも生成 AI・大規模言語モデル(LLM)の実用化に取り組む企業が目立ったことです。
ストックマークの「Stockmark-LLM-100b」、Deepreneur の「Blue-Lizard」、Kotoba Technologies の同時通訳 AI、Kotozna の多言語 AI チャットボットなど、基盤技術の開発から具体的なアプリケーションまで幅広くカバーしています。
生成 AI・大規模言語モデルの実用化加速
2025年上期最大のトレンドは、生成 AI・LLM の実用化が本格的に加速したことです。多くの企業が研究開発段階から商用展開段階に移行しており、その背景には技術の成熟度向上と具体的なビジネス課題の解決があります。
例えば、ストックマークは独自開発の LLM「Stockmark-LLM-100b」を公開し、企業向けの情報活用プラットフォーム「Aconnect」や文書構造化サービス「SAT」を展開しています。同社代表取締役 CEO の林達氏は「生成 AI 時代におけるデータの重要性は言うまでもないが、文書主義である日本は、多くの大企業が大量の資産を有しており生成 AI 時代でも優位にある」と語っています。
一方、Deepreneurは AI の松尾・岩澤研究室発の AI スタートアップとして、独自 LLM「Blue-Lizard」を中心とした企業向け DX ソリューションを提供。同社 CEO の澤田悠太氏は「AI 技術を用いてこれまでにない新しい人間とテクノロジーの関係を築く」というミッションを掲げています。
このほか、人手不足が深刻化する中、既存産業の DX・効率化に特化したソリューションも目立ちます。IVRyは対話型音声 AI SaaS「IVRy」を月額2,980円から提供し、電話応答業務の自動化を実現。同社 Enterprise&Strategic Account の武田和曉氏は「働くことは楽しいを常識に変えていく」ことを目指しています。
AI領域12社紹介
- 筑波大学発 AI スタートアップ – AIdeaLab
- 生成 AI で企業変革を支援 – ストックマーク
- グローバルに認知される独自の生成 AI 開発 – データグリッド
- AI 総合研究所として活動する東大発スタートアップ – NABLAS
- 米国トップ校の AI 分野で博士号取得メンバーが起業 – Kotoba Technologies
- 東大松尾・岩澤研究室発 AI スタートアップ – Deepreneur
- 人間の脳を模した AI プラットフォーム – グラフェン・ジャパン
- エッジ AI 向けファブレス半導体の開発・設計 – EDGECORTIX
- AI 用データの個人情報非識別化技術を開発 – Deeping Source
- 電話自動応答システムを作成できる月額制サービス – IVRy
- 固有情報に基づく多言語 AI チャットボットを開発 – Kotozna
- 食×テクノロジーで健康を支える – シルタス
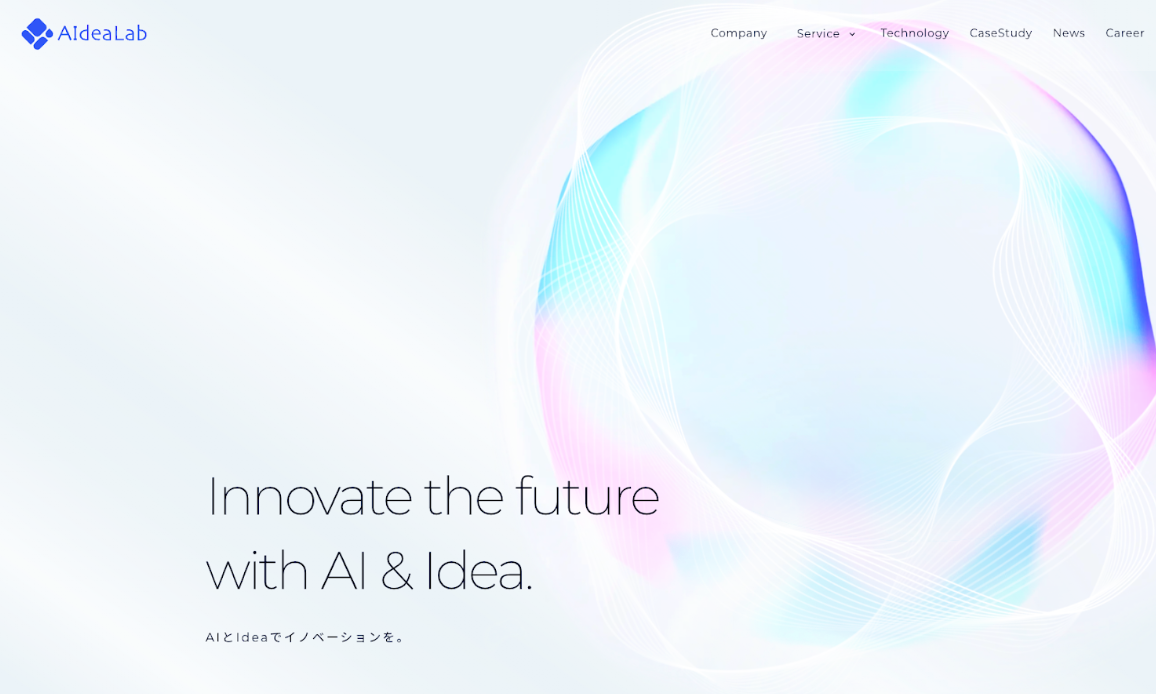
AIdeaLabは、筑波大学発のAI領域に特化したスタートアップスタジオです。代表取締役の冨平準喜氏が率いる同社は、2つの事業を展開しています。
1つ目は自社開発プロダクトの展開で、「AI ピカソ」(日本初の画像生成 AI モバイルアプリ)、「AI 素材.com」(AI 生成画像の素材サイト)、「AI 議事録取れる君」(AI を活用した議事録サービス)、「AI ひろゆき」(有名人初の AI アバター)などを開発。
2つ目は企業や研究機関と連携した AI ソリューションの提供で、生成 AI や大規模言語モデル(LLM)の技術を用いてパートナー企業の課題解決や新規事業の創出をサポートしています。
同社は独自開発した AI モデルの API 提供やカスタマイズも行い、多岐にわたる分野での応用を実現。様々な分野のパートナーとの協業や共同研究を通じて、人々の生活を豊かにする新たな価値の創造を目指しています。

ストックマークは、生成 AI 技術を活用した企業変革を支援するスタートアップです。代表取締役 CEO の林達氏は台湾出身で、伊藤忠商事での経験を活かして AI による情報処理の革新に取り組んでいます。
主力サービスは、社内外の情報をワンストップで検索できる「Aconnect」と、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT(Stockmark AI Technology)」です。同社は独自開発の LLM「Stockmark-LLM-100b」を公開し、国内オープンモデルの中でも最高性能を記録しています。
同社は企業特化生成 AI の開発や独自システムの構築も支援。複雑で非定型な社内文書を AI-Ready、RAG-Ready なデータに変換する「データ構造化」技術を活用し、企業の AI 活用を推進しています。
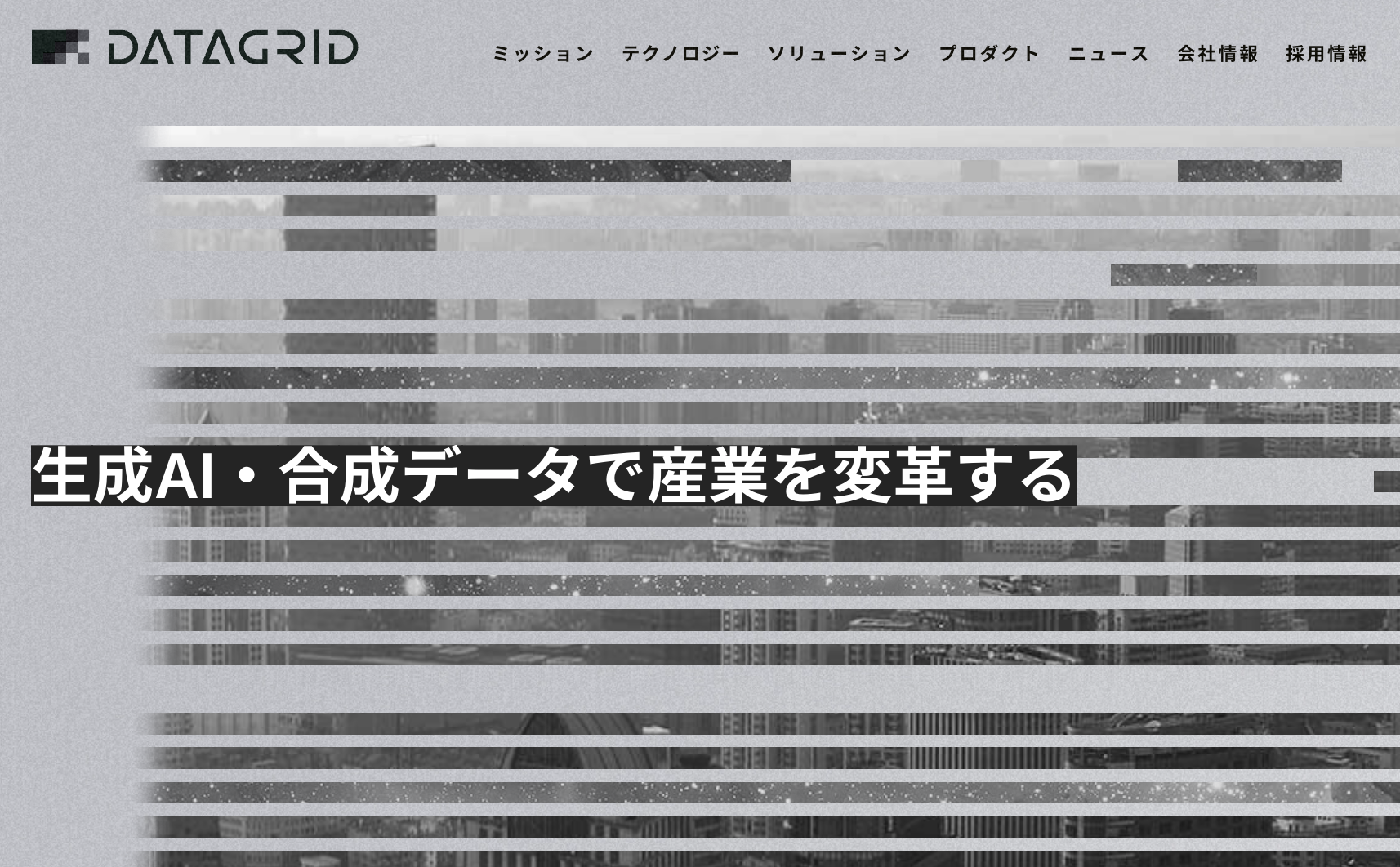
データグリッドは、2017年に創業した京都大学発のスタートアップで、生成 AI の黎明期から研究開発に取り組んでいます。代表取締役 CEO の岡田侑貴氏は、祖父や父の事業経営の姿を見て育ち、世界中のたくさんの人に使ってもらえるサービスを作りたいという想いから起業しました。
主力プロダクトの「Anomaly Generator」は、製造業の外観検査で不足しがちな不良品画像の教師データを生成 AI で合成し、検査 AI の精度を改善するソフトウェアで、製造現場の AI 化を支援しています。
同社は大規模言語モデル(LLM)、動画・画像生成 AI、音声生成 AI を活用し、製造業をはじめとした各産業特有のデータを基にカスタマイズ開発した生成 AI ソリューションを提供。教師データを生成 AI で合成することで、多様なパターンを網羅した学習データセットを構築しています。
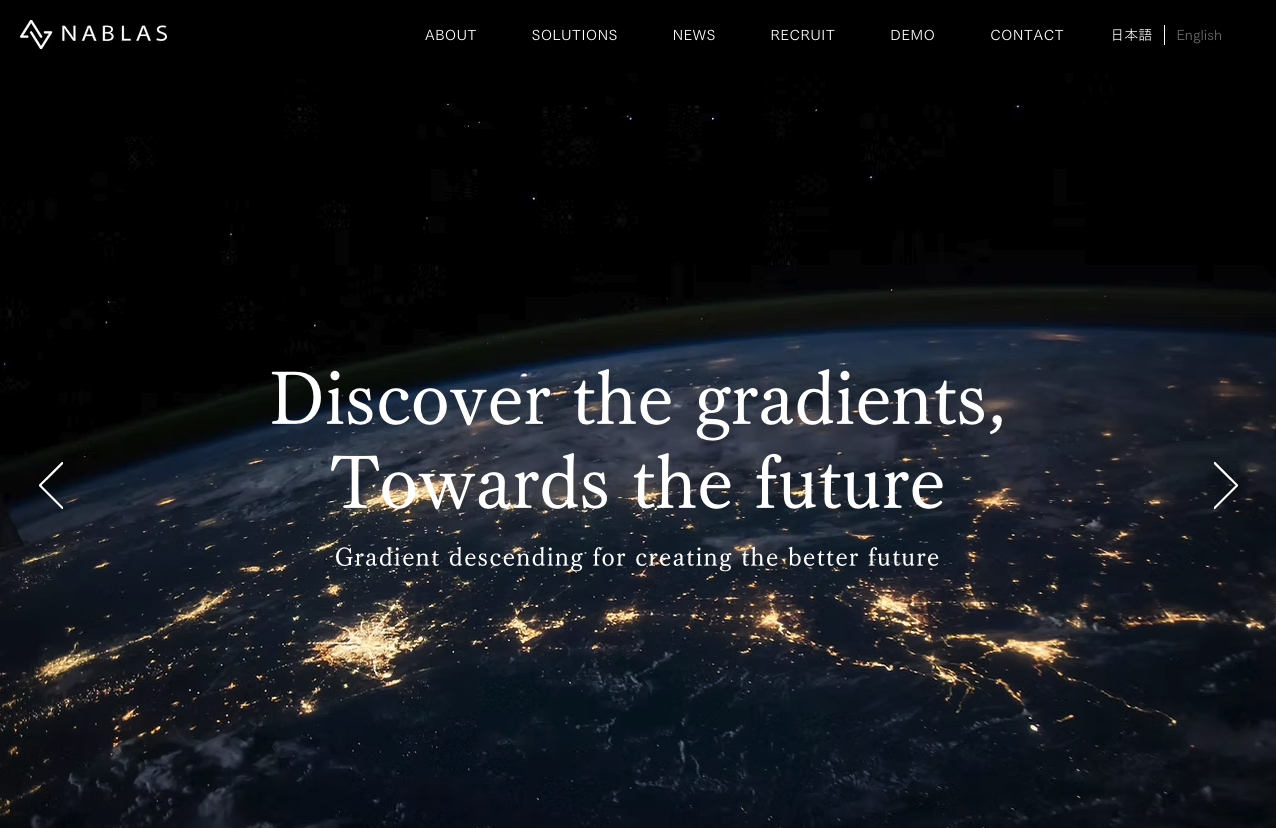
NABLASは、AI 総合研究所として、総合商社から自動車メーカーまで幅広い業界で機械学習を活用したコンサルティングを手掛けています。リサーチャーの新立拓也氏は、食品・流通小売領域に特化したマルチモーダル大規模モデル「NABLA-VL.food」を開発中です。
このサービスは、社内データベースや SNS 上の食べ物に関する膨大なデータを LLM で分析し、トレンドの抽出や注目の食べ物・地域・ターゲット層の抽出、標準化されたデータベースの自動作成などを行います。小売業の企業から「社内に標準化されたデータベースが存在しない」という声を受けて開発されました。
同社は機械学習を活用したコンサルティングや共同プロジェクトに加え、自社プロダクトの開発にも取り組んでいます。また、AI 人材育成にも力を入れており、「iLect」という実践的な AI 講座提供サービスも展開しています。

Kotoba Technologiesは、2023年9月に創業された日米クロスボーダーの生成 AI スタートアップです。Co-founder&CEO の小島熙之氏は、コーネル大学とワシントン大学でコンピューターサイエンスの博士号を取得したメンバーと起業しました。
同社は音声分野の生成 AI 技術に注力し、リアルタイム音声基盤モデルの開発と日本市場における実用化を進めています。リリース直後に Apple Store で5位にランクインしたこともある iOS アプリ「同時通訳」を提供し、誰でもリアルタイムで多言語コミュニケーションを実現できるサービスを展開しています。
また、イベント向けの web アプリや開発者向けの SDK/API といった形でも技術を展開し、幅広いシーンでの活用を支援しています。GENIAC の第1.5回および第2回にも採択されており、グローバル規模での展開を目指しています。

Deepreneurは、東京大学松尾・岩澤研究室発の AI スタートアップです。CEO の澤田悠太氏は、独自 LLM「Blue-Lizard」を中心とした企業向け DX ソリューションを提供しています。
同社は業務フローをもとに課題を分析し、技術コンサルティングから技術検証、本開発、導入までを一気通貫で支援。会社固有の課題に対して、業務フローやデータ分析を行い、独自の AI 技術を用いて業務の効率化・高度化を図る DX ソリューション事業を展開しています。
変化の激しい生成 AI に対応するため、従来の一度大量のデータで学習した AI モデルを使い回すスタイルではなく、モデルの入れ替えや追加学習などの柔軟性を考慮したアーキテクチャを採用。Forbes Japan「JAPAN'S AI 50 日本発 AI スタートアップ50選」にも選定されています。
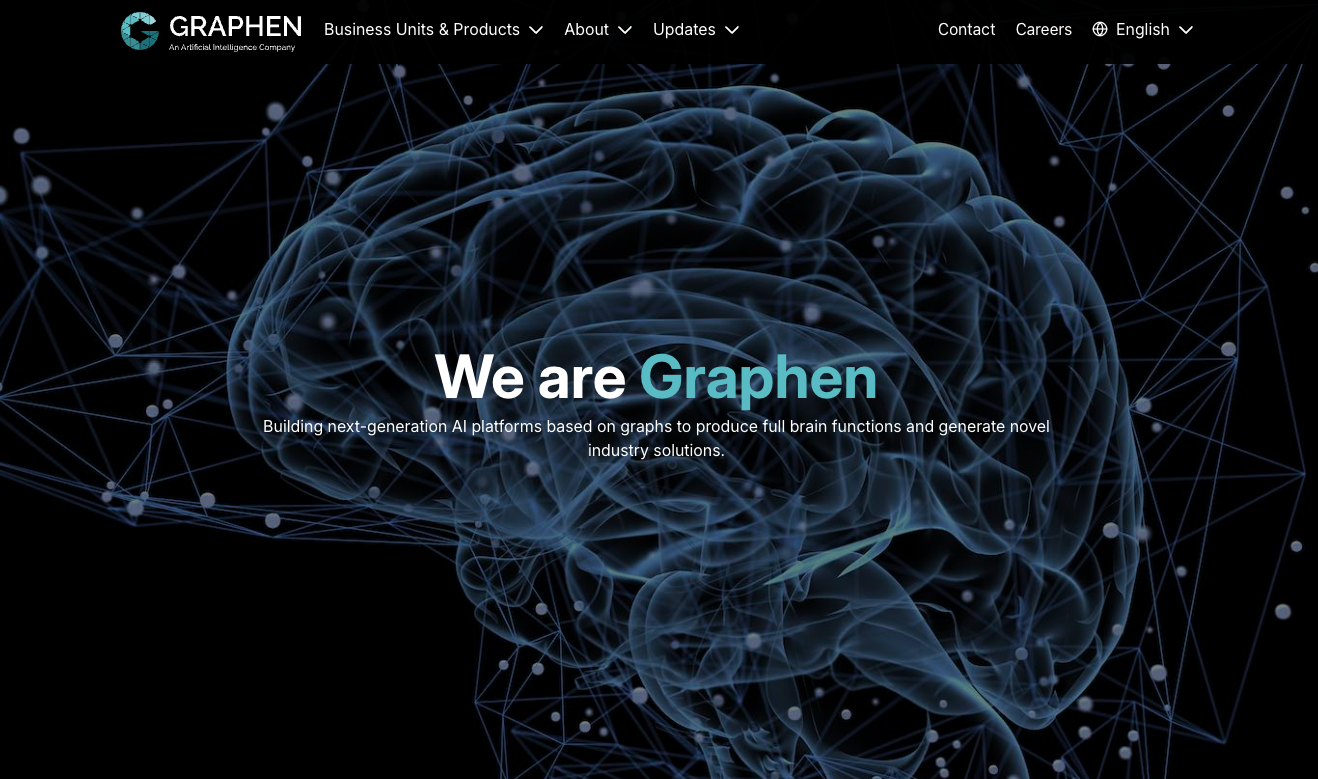
グラフェン・ジャパンは、2017年米国 NY で設立した Graphen, Inc. の日本法人として2023年10月に設立されました。代表取締役社長の前島忠人氏は、元 IBM チーフサイエンティストでワトソンの開発責任者であった Dr.Lin が創業した AI 技術を日本市場に展開しています。
同社の AI プラットフォーム「Ardi」は、グラフ機能を強化し推論機能で人間の脳のように動作する先端 AI です。機械学習・深層学習とは異なり、少ない情報・データ量でも高精度の判断を小さなマシン能力で実現する点が特徴です。
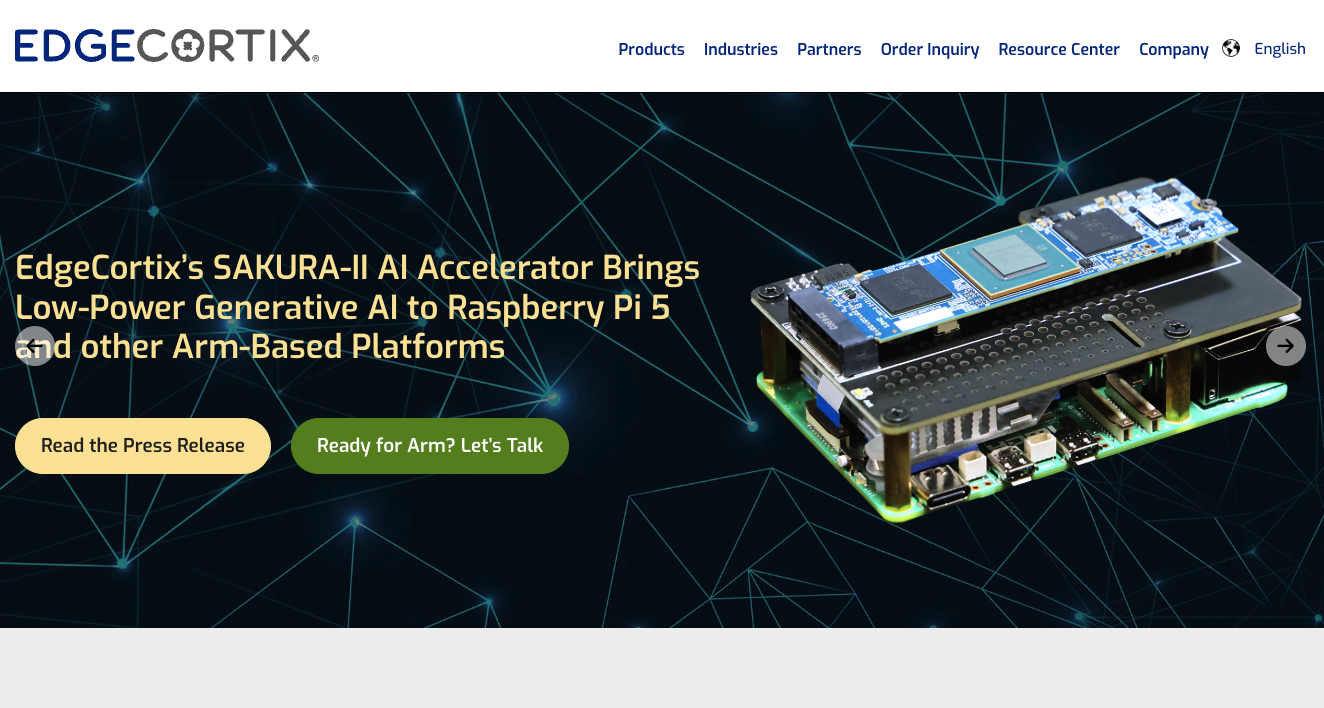
EDGECORTIXは、エッジAI向けのファブレス半導体開発・設計を手掛ける企業です。創業者兼 CEOのダスグプタ・サキャシンガ氏は、AI 処理と消費電力のギャップを解決する技術開発に取り組んでいます。
同社はソフトウェアとハードウェアの協調設計という独自の特許技術を活用し、高速かつ低消費電力で柔軟なエッジ AI 専用プロセッサを開発。主な製品には、ランタイムで再構成可能なニューラルネットワークプロセッサ IP「Dynamic Neural Accelerator(DNA)」、マルチハードウェアプラットフォーム対応コンパイラ「MERA」、エネルギー効率に優れた AI コプロセッサ「SAKURA」シリーズがあります。
これらの製品は、防衛、航空宇宙、スマートシティ、インダストリー4.0、自動運転システム、ロボティクスなど、多岐にわたる分野での活用が期待されています。

Deeping Sourceは、個人情報を完全に保護しながらデータの価値を維持する独創的な匿名化技術を開発しています。CEOのPete Tae-hoon Kim氏は、AI 技術の活用可能性が無限に拡大する一方で、個人情報侵害という倫理的・法的問題がその成長を妨げてきた課題に取り組んでいます。
店舗運営ソリューション「Plus Insight」は、コンビニ、ドラッグストア、スーパー、遊園地、展示場などの空間において、顧客とスタッフの全ての行動データを映像ベースの AI 技術でリアルタイムに収集・分析し、店舗運営を改善して収益性を最大化する Agentic AI ソリューションを提供しています。
Agentic AI は、収集されたデータに基づいて店舗スタッフに最適な業務指示を出し、店主に効果的な運営戦略を提案し、スーパーバイザーに優先的に訪問すべき店舗と主要管理ポイントをリアルタイムで知らせるなど、各ユーザーの役割に応じた差別化された価値を提供します。

IVRyは、対話型音声 AI SaaS「IVRy」を月額2,980円から提供しています。Enterprise&Strategic Account の武田和曉氏は、AI やソフトウェアの力で業務を効率化し、人の介在価値を最大化することで「働くことは楽しいと皆が感じられる世界を作りたい」と語っています。
IVRy は電話応答の分岐や、AI による自動応答・予約代行など豊富な機能を利用でき、仕組みも直感的に操作できるよう設計されています。導入企業は中小企業から大企業まで規模はもちろん、業種も問わず全国で幅広く導入されており、2024年11月末時点で47都道府県・94業界以上のアカウントを発行し、累計着電数も大きく増加しています。
2025年1月31日には「シゴトシフト2025 - AI で現場が楽になる -」というカンファレンスを開催し、人手不足が進む社会の中で生成 AI を活用した業務効率化やコア業務に集中できる環境づくりのヒントを提供しています。

Kotoznaは、生成AIを活用した多言語チャットボット「Kotozna ConcierGAI」を開発しています。代表取締役の後藤玄利氏は、ケンコーコムでインターネットが社会を変革する可能性を実感し、次は AI 技術を活用して社会課題を解決することに挑戦しました。
同社のサービスは、クライアントの固有情報に基づき、生成 AI が正確な回答を多言語で自然に提供。観光業界を中心に、国内外500以上のホテル、大阪観光局、シンガポール・チャンギ空港などでの導入実績を持ち、言語の壁を超えたコミュニケーションを支援しています。
現在開発中の CMS により、業務知識だけで AI チャットボットを作成できる環境を提供し、中小企業がコストを抑えつつ、グローバル市場で競争力を高める機会を創出します。多国籍で多様性を重視した組織を作り、グローバル市場で戦える企業を目指しています。

シルタスは、購買データを活用した栄養管理アプリ「SIRU+」を開発しています。代表取締役の小原一樹氏は、日々の食事をほとんどの人が"なんとなく"で選んでいることに不健全さを感じ、「食の楽しみ」と「将来の健康」を両立させる仕組みが必要だと考えました。
SIRU+ は「栄養データの自動取得」と「行動変容」をメインコンセプトとし、買い物の履歴を自動で栄養データに変換し、日々の買い物から健康を目指します。既存の栄養管理サービスが健康関心層をターゲットにしているのに対し、SIRU+ は健康非関心層でも簡単に続けられるサービスを目指しています。
同社はスマートシティや PHR、情報銀行などのプロジェクトにも参画し、小売・流通や食品メーカー、保険など幅広い分野の企業および自治体と業界を超えたデータの利活用を行っています。生成 AI を活用して、購買誘導からファン化までを一貫支援する統合マーケティング支援ツールとしての価値も強化しています。
まとめ
第1弾では、2025年上期の最大のトレンドである AI領域の12社をご紹介しました。これらの企業に共通するのは、生成AIやLLMの技術を単なる研究段階から実用段階へと押し上げ、具体的なビジネス課題の解決に取り組んでいることです。
次回第2弾では、DeepTech、サステナビリティ領域の企業をご紹介しますのでお楽しみに!
関連リンク
関連記事
-

素材の力で未来を創る - マテリアルゲート
2026年02月03日
-

ニッポン発、今ここにない未来をつくる - POCKET RD
2026年01月29日
インタビューの記事
-

MUGENLABO UNIVERSEから生まれた新たな教育の形 ― ライフイズテックとアストロスケールが描く「宇宙×デジタル」の未来
2026年02月10日
-

素材の力で未来を創る - マテリアルゲート
2026年02月03日